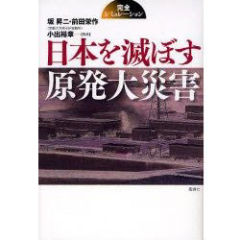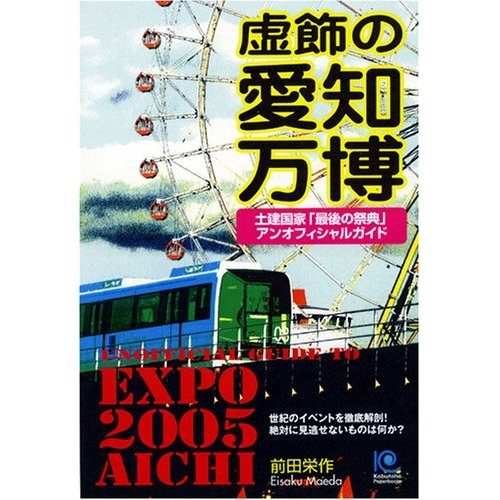「昭和十七年生まれがいなくなったなら……」<祭り・ニワトリの世話・五右衛門風呂>福井 章著
 祭り
祭り
祭り囃子の音がかすかに聞こえてきた。祖父母と私の三人は、いつもより早めの夕食を終えると、歩いて十五分ほどの街中へと歩いていた。私は普段と同じ膝下くらいまでしかない絣の着物を着ていた。それでも心は華やいでいた。
その日、年に一度の夏祭りが行われるのだ。町へと近づくにつれ笛や太鼓の音が徐々に大きく聞こえてきた。目的は夏祭りで曳かれる山車である。私たちと同じように山車を見物するため、近在から多くの人が集まっていた。時間の経過とともに人の数は膨れ上がっていった。堤防から天竜川へこぼれ落ちてしまうのではないかと思われるくらい多くの人、人、人であった。東京にいた時も見たことのないくらいの人の多さに怖くなり、思わず祖父母の手を満身の力で握りしめていた。
何とか山車を間近でみられるところまで、人波をかき分けていった。「どうだ、よく見えるか」といって祖父は私の両脇に手を入れ、ひょいと肩車してくれた。「うん。とってもきれい」。
祭りの御神輿は見たことはあるが、それとは比べられないほど大きく、家くらいの大きさの山車を見るのは初めてだった。当時は唐破風づくりだとか彫刻という言葉は知らなかったが、山車の一番上にある屋根の下にきれいな飾りがあり、ぐるりと周りが幕で囲まれ、何人もの人が乗って笛を吹き太鼓を鳴らしていた。全体に提灯が吊るされひときわ山車を明るく浮かび上がらせていた。
静岡へ来るまでの東京の記憶といえば焼け野原しかなかった。満足に食べるものがなく、いつも空腹を抱えていた。それに比べ、この祭りの華やかさと人々の楽しそうな振る舞いは、まさに天国と地獄のような差だといっても決して大げさではなかった。
祭りが終わり、祖父母に手を引かれての帰り道でも私の中では祭りが続いていた。笛を吹き、太鼓を敲く真似をしていた。家に帰ってからも、布団に入るまでその興奮は冷めずに続いていた。
ニワトリの世話
普段着といえば、夏はひざ下くらいまでしかない絣の着物、履物は祖父が作るワラジであった。
一日の始まりはニワトリの餌作りである。祖父母の家では数羽のニワトリを飼っていた。当時、ほとんどの農家ではニワトリを飼っていた。街中でもニワトリを飼っている家があった。目的は卵である。ニワトリの餌は、大抵は野菜くずを細かく刻んだものであった。祖父が作った餌をニワトリに与えるのは私の仕事であった。餌を与えるときはかならず「コーコッコ、コーコッココ」といった。私がニワトリに餌をやっている間に、祖父は農作業に必要な機具をリヤカーに積み込む。そうしているうちに、祖母が朝食の支度をする。朝食を済ませると、三人で畑へ出かけた。
祖父がリヤカーを引き、祖母が後ろから押す。私は祖母と一緒にヨイショ、ヨイショと声を出してリヤカーを押すのを手伝ったり、リヤカーに乗ったりする。道端できれいな花を見つけると、それを摘み、この花、なんていう名前?と祖父母に聞く。バッタを見つけると追いかける。そうこうしているうちに畑に着く。祖父母は畑仕事に精を出し、小さな子どもと遊ぶ暇はないが、それなりに見つけ出した遊びで一人でも楽しく時間を過ごす。
昼は畑の横にあった木の下で握り飯やサツマイモを食べた。たまにはおかずのついた弁当を広げることもあった。
家で食べる野菜などを収穫したときは祖母が背中の竹かごに入れて担いで帰る。祖父はそのまま畑仕事を続ける。行きとは違い、帰りは歩きとなる。行きよりもたくさん遊べる。祖母も一緒になって遊んでくれた。
家に帰ると再びニワトリへの餌やりである。祖母が刻んだ野菜くずなどを、私がコーコッコ、コーコッココといいながら与える。その時、卵があれば取ってくる。当時、都会では卵はめったに食べられないぜいたく品であった。それが毎日とはいかなくても、少なくとも二~三日に一回は一~二個くらいの割で口にすることができた。
生みたての卵は卵焼きやゆで卵になった。あるいはその日に収穫したばかりの新鮮な野菜で作ったオジヤの中に入れ、塩で味付けした。砂糖はまだ貴重品で、これといった調味料もなかったが、本当においしかった。
五右衛門風呂
納屋を改築した祖父母の家に風呂はなかった。現在では風呂のない家は考えられない。しかし、昭和二十年代、三十年代、風呂付の家の方が珍しかった。町では銭湯へ行く人の方が多く、家にある風呂を内風呂、銭湯などを外風呂と呼んでいた。
夕食を終えると、隣にある祖母の実家の小栗家の風呂を使わせてもらっていた。近隣の家の風呂を使わせてもらうことを「もらい湯」と呼んでいた。祖父がまずもらい湯をした後で、私と祖母がもらい湯に行く。風呂から上がると。小栗家の人に「ごちそうさまでした」と礼を述べて帰ってくる。
小栗家の風呂は五右衛門風呂であった。石川五右衛門が釜茹での刑にされたのと同じように、鉄製で大きな釜のような形をしている。下から直接薪などを燃やして水を温める。そのまま入ると風呂の底に足が触れ、火傷する。
風呂のふたを開けると、丸い簀の子が浮かんでいる。その上に足を乗せ、まっすぐ下まで沈める必要がある。体重が簀の子全体にかかるよう、足を真ん中に乗せるのだが、バランスがとれないとうまく沈まないばかりか、簀の子が足から外れ,勢いよく浮き上がってしまう。コツさえ飲み込めば、決して難しくはない。
最初は祖母が簀の子を上手に沈め、私を抱っこして入れてくれていたが、そのうち、一人でも簀の子を沈めることができるようになってきた。ある日、一人で入ろうとして、簀の子を踏み外してしまった。足の裏が風呂底に直接触れてしまった。慌てて風呂から飛び出したものの、火傷が痛くて大声で泣いた。その後二~三日は足をつけて歩くことができなかった。
・・・・・<ワラジ・戦争の悲劇・お汁粉>へつづく
「昭和十七年生まれがいなくなったなら……」<カラスの贈り物・おやつになった雑草や昆虫>福井 章著
 カラスの贈り物
カラスの贈り物
祖父母の家のすぐ横には小さな水路が流れていた。水路とはいっても、コンクリート張りではなく、自然の小川のような雰囲気であった。農作業から帰ってきた祖父母がその水路で鍬や鋤をよく洗っていた。水の中にはメダカが泳ぎ、初夏ともなれば蛍が乱舞した。餌になるカワニナが生息できるくらい水がきれいであったということだ。街路灯もなく、真っ暗な初夏の夜に飛び交う蛍の光はまさに幻想的な光景であった。
二人だけの暮らしに孫が加わり、祖父母もどこか楽しそうであった。私も母がいない寂しさより、東京でのひもじい暮らしから一転し、毎日、お腹いっぱい食べられる生活に満足していた。
浜松も市街地は空襲によって大きな被害を受けていた。しかし、掛塚は幸いにも空襲の被害はなかったようだ。焼け野原となった東京とは違い、ここには平和で豊かな暮らしがあった。
祖父母が農作業へ出かけるときは、私もついていった。祖父が引くリヤカーに農機具と一緒に乗り、後ろから祖母が押す。三〇分ほどで畑に着く。野菜の収穫、雑草取りなどを手伝った。もちろん小さな子どもだから手伝うといっても祖父母の真似をするだけで、むしろ農作業の足手まといになっていたかもしれない。
遊び道具など何もないが、虫を捕まえたり、花を摘んだり、時には畑の片隅で穴を掘ったり、土をこねるなど、結構楽しかった。畑で作業をしながら、一人で遊ぶ私を、祖父母はいつも優しく見守ってくれていた。
ある日、町へ売るためのスイカを収穫するために畑へ出かけた。カラスが数羽、畑の近くを飛んでいた。スイカを収穫していると、明らかにカラスがつついた痕のあるものが幾つかあった。キズものになったスイカは売れなくなる。祖父は「チクショウ、カラスのやつめ」、と罵り声をあげながら、近くを飛んでいるカラスに向かって手に持っていた鎌を振り上げた。
「カラスもそうだが、ほかの鳥も食べごろかどうかよく知っている。鳥がつついたものはおいしいんだ」といって、キズのついた部分を鎌で切り取り三人で食べた。冷えてはいないが甘く、暑い夏場の農作業にとってはひと時の涼となった。
おやつになった雑草や昆虫
祖父母の家は天竜川の堤防から五〇メートルほど離れた場所にあった。畑仕事がなく天気の良い日には天竜川の河原へ釜戸で燃料にする流木を拾いに出かけた。河原には上流から流れて来た流木がたくさんあった。大きなものもあれば、小枝もある。祖母はよく乾いた小枝を拾い、背中の竹かごにポイ、ポイと手際よく放り込んでいく。二時間もすればかご一杯になる。小枝を拾い集めるだけのことだが、なんとも楽しかった。
そしてもう一つ、河原には楽しいことがあった。この地方でアマジと呼んでいた草があった。土手に生えているこの草を素手で掴んで引っ張ると、淡いピンク色をした根っこが採れた。手で土を拭い落とし、そのままシャキシャキかじるとほんのり甘い汁が口の中に広がった。お菓子はもちろん、甘いものそのものが乏しかった時代である。今となっては正式な名前もわからない。いまなら同じようにかじったとしても、甘いと感じるかどうか、わからない。それでも当時の子どもにとっては格好のおやつ替わりとなった。
甘いものと言えば、この辺りには生垣に「ほそば」という木が使われていた。ほそばはこの地方の方言で、槇の木のことである。夏の終わりから秋にかけ直径一センチほどの、雪だるまのような形をした実がつく。上が赤く下になった部分は青い。この実をヤンゾウ、ニンゾウと呼んでいた。赤い部分は淡い甘さがあり、その実が熟して紫色になるとさらに甘みが増し、ゼリーのような感触になった。子どもにとっては極上のおやつであった。
近所に住んでいた小学生の男の子が、よく私と遊んでくれた。その子が稲刈り前になると、田んぼにいるイナゴ取りにつれて行ってくれた。イナゴは人をあまり警戒しないのか、四、五歳の子供でも簡単に取れた。袋を一杯にして帰ると、祖母が「沢山捕れたね」といって私を褒めてくれた。そして翌々日には佃煮になって食卓を飾った。普段は野武士のような顔つきの祖父であったが、目を細め「アッ君が捕ってきたイナゴ、いただきます」といって喜んで食べてくれた。もちろん私もたくさん食べた。
足長バチの幼虫もよく食べた。巣を見つけると、細長い竹で叩き落して巣を持ち帰り、中にいる幼虫を一つずつつまみ出す。それを祖母にフライパンで炒ってもらい、おやつにした。
雨さえ降らなければほとんど毎日のように、決まった時間に行商のおばあさんがやってきた。そのおばあさんを、みんなは「ハッチャー」と呼んでいた。腰が曲がり、籐で編んだ乳母車を杖代わりにするかのように前かがみになって押していた。どんな商品を中心に売っていたのかは知らないがたまに祖母から小遣いをもらうと、ハッチャーが来るのを楽しみにしていた。
家の外で待っていると、やがて遠くにハッチャーの姿が見える。急いで走って迎えに行き、一緒に乳母車を押して家の前までくる。私が好きだったのは、甘辛く煮込んだイカであった。それを一匹丸ごと買って、祖母と一緒に食べるのが楽しみであった。もしかすると、祖母に母の姿を重ね合わせていたのかもしれない。
・・・・・<祭り・ニワトリの世話・五右衛門風呂>へつづく
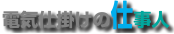
 福祉系情報誌の編集は得意分野です。日常持ち合わせている情報やネットワークを生かし、企画・取材・執筆・編集承っております。
福祉系情報誌の編集は得意分野です。日常持ち合わせている情報やネットワークを生かし、企画・取材・執筆・編集承っております。
 次へ ≫
次へ ≫