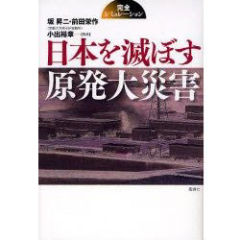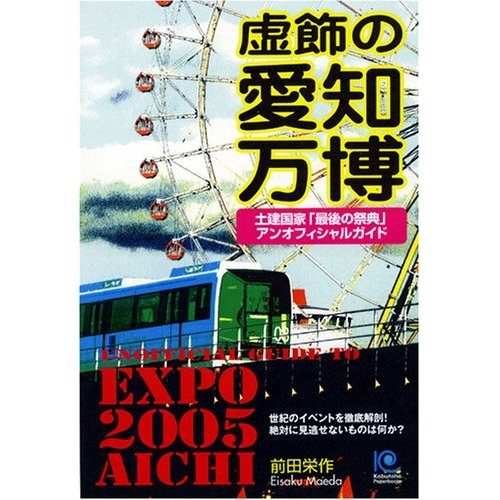「昭和十七年生まれがいなくなったなら……」<おみ君のおっぱい・台所で倒れこんでいた私>福井 章著
 おみ君のおっぱい
おみ君のおっぱい
昭和二十年八月六日に広島、九日には長崎に原子爆弾が投下され、日本は十五日に無条件降伏を受け入れた。昭和六年(一九三一)の満州事変から続いた十五年に及ぶ戦争がようやく終わった。軍部の一部には最後の最後まで戦うと叫んでいた者もいたようだが、国民の多くは平和になったことを喜んだ。母も「ああ、やっと戦争が終わってくれた」と安堵したという。
だが、戦争が終わったからといっても相変わらず国民生活は窮乏していた。戦争が始まるころから生活物資の不足を補うために切符配給制がとられていたが、物不足はますます酷くなっていた。特に主食の米は、敗戦間際には大人一人一日当たり約三百グラム、子どもは約二百グラムの配給となっていたが、それも二か月や三か月の遅配は当たり前となっていた。
どうやって生活をしていたのか不思議に思い、当時のことを母に訊ねてみた。
「満足に食べるものがなく、毎日ひもじい思いをしていたと思うけど、どうやって生きていたのだろうかね、思い出せないね」と悲しそうな表情を浮かべ、つぶやくように答えてくれた顔がいまも忘れることができない。
敗戦の約一年前の昭和十九年に弟が生まれていた。私は四歳になっていた。十分な食べ物がなく、大人でも生きることで精いっぱいの時、子どもはもっと厳しい状況の中にいた。空襲の恐怖から解放された九月のある日、その日はまだまだ夏の暑さが残っていた。
一歳になったばかりの弟が母の乳を飲んでいた。私は弟を見つめ「おみくん、おいしい?」と声を掛けた。私が発した言葉を聞いた母は「アッ君もここに来ておみ君と一緒にお飲み」といって手招きした。
だが私は「ダメ! おっぱいはおみくんの」と強く拒否し、座ったまま後ずさりした。
昭和二十年の東京大空襲は従来の軍事施設を狙ったものとは異なり、人口の密集した下町などを中心に行われ、民間人が大量に焼死した。こうした空襲の結果、流通も大きな被害を受け、食糧事情はさらに悪化していた。食べ物がほとんど手に入らない状況の中、乳呑児を抱える母親の栄養も悪く、子どもに十分な乳を与えることができず、子どもたちの体力は日に日に衰えていった。弟のおみくんの体力もかなり落ちていた。乳離れをしていたとはいえ、私の体力もかなり衰えていたと思われる。
母はそんな我が子の体力が落ちていくのがつらく、弟を寝かしつけると涙をぼろぼろ流しながら、ぎゅっと抱きしめ「おみ君は一杯飲んだから、今度はアッ君が飲みな」といって胸を私の顔に押し当ててきた。
それでも「ダメ、これはおみくんの」と言って、両手で強く母の胸を押しのけるのであった。母はそれでも「お願いだから飲んで」と無理矢理にでも飲ませようとするのだが、私は部屋から逃げ出した。まだ幼かったにもかかわらず、飲めば弟のおみ君の分がなくなってしまうという気持ちがあったようだ。
台所で倒れこんでいた私
戦争が終わり、アメリカ軍が日本に進駐した。進駐軍が使用するため、多くの建物が接収された。公共輸送も進駐軍優先であった。それでも敗戦の翌年あたりから少しずつ改善され、東海道本線に急行列車が運行されるようになった。ただ、食糧事情は相変わらず悪いというより、むしろ悪化していた。
昭和二十年の東京大空襲によって池袋も一面の焼け野原となっていた。当時、私の実家は板橋区(現練馬区)江古田町にあった。空襲の時、私より十歳上の兄は燃え盛る火のため、家の中でも本が読めるほど明るかったと言っていた。
戦争が終わると、焼け野原の中にヤミ市が現れるようになった。ヤミ市へ行けば大抵のものは手に入れることができたが値段はべらぼうに高かった。
米や野菜など、普通の店へ行っても簡単に手に入れられなかった。そこで近在の農家を訪ねては直接交渉しながら買い付けした。時には着物などと交換することもあった。たとえサツマイモが一個しかないと言われても買った。
食料を手に入れるため、時にはリュックサックを背負い、自宅から二〇キロ、三〇キロも離れた川越まで歩いて出かけることもあった。往復すれば五〇~六〇キロになる。食料が手に入れば背中のリュックは重くなる。朝、暗いうちに家を出て、家に帰りつくころは夜中である。
戦後処理のため、猛烈なインフレが進み、昭和二十一年二月に新円切替が行われることになった。同じ一円であっても、それまでの一円と新円の一円では価値が大きく異なる。そのため、預金封鎖が行われ、一世帯当たり、銀行から一か月に引き出しのできる金額は五〇〇円以内に制限されてしまい、使用できる現金も少なくなった。
窮乏生活の中で必死になって蓄えた国民のお金を、国は預金封鎖によって最後の一円までも取り上げたのである。
そこで物々交換で食料を手に入れることが多かった。
その年の六月、配給の乾パンを受け取って帰宅した母が、台所でうつ伏せになって倒れている我が子を発見した。驚いて手にしていた荷物を放り投げて子どもの横に座り込んで抱きかかえ、「アッ君、アッ君。起きて、起きて。どうしたの、目を開けて、お願い」と大声を出して必死になって呼びかけた。
母の思いが子どもに通じたのか、うっすらと目を開けた。だが、すぐに目を閉じてしまった。
幸いにも大事に至ることはなかったが、このままではこの子は死んでしまう、一刻も早く祖父母がいる静岡の掛塚へ連れていき、療養させなければと考えた。そこは祖母の実家で、畑を作っていたので、食べるものだけはあった。
夜になり、買出しから戻ってきた父に事の顚末を話し、私が小学校へ入学するまで掛塚で預かってもらうことになった。祖父母に連絡している余裕などない。翌日、東京駅に向かい、父が切符を二枚手配し、一番列車に母と弟の三人で乗り込んだ。
この時の母は、四歳にになって間がない幼い子が親元から離れ、祖父母と三人でうまく生活に馴染めるだろうかなどと考える余裕などはなく、掛塚へ行けば何とか食べることだけはできると思ったという。それほど食糧事情は逼迫よくしていた。
・・・・・<家族と別れ静岡へ・おにぎり・何か月ぶりかのお米のご飯>へつづく

 福祉系情報誌の編集は得意分野です。日常持ち合わせている情報やネットワークを生かし、企画・取材・執筆・編集承っております。
福祉系情報誌の編集は得意分野です。日常持ち合わせている情報やネットワークを生かし、企画・取材・執筆・編集承っております。