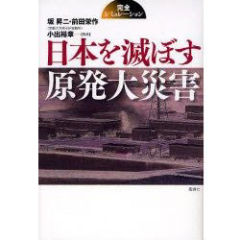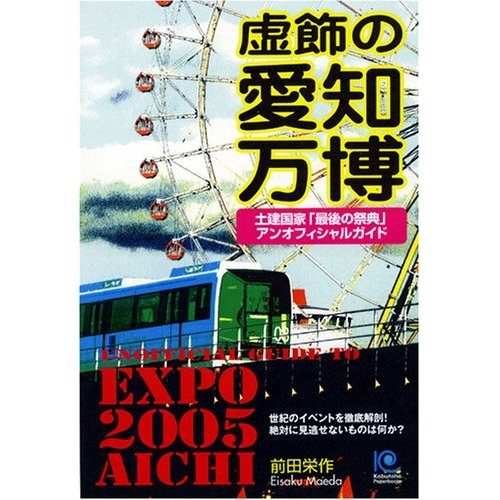「昭和十七年生まれがいなくなったなら……」<別れの日・終わらない戦争の傷跡・あとがき>福井 章著
 別れの日
別れの日
天竜川が荒れ狂った日から数日が経った。川は何事もなかったかのように穏やかな表情で流れていた。祖母と二人で流木を拾いに出かけた。いつもと違うのは大水のおかげであっと言う間にかご一杯の流木が集まったことだ。
流木拾いの手を休め、東海道線の鉄橋を見つめながら、もうすぐお母ちゃんが迎えに来るね、と祖母がボソリという。その言葉を聞かされる度に、寂しい気持ちに襲われた。汽車が汽笛を鳴らして鉄橋を渡るのを見るだけで悲しい気持ちになった。そうした日々を重ね、やがて、汽車そのものが悲しい思い出になっていった。
夏が終わり秋になった。妹を背負った母がやってきた。母が来て三日ほど経ったところで、祖母と母、それと私の三人で浜松にある朝比奈家の本家へ、明日、帰京するとの挨拶に行った。
掛塚の家に戻ると、当時としてはおそらく最高の贅を尽くしたと思われる料理が食卓に並んだ。どんな料理であったのかは覚えていないが、それまで口にしたことのないようなものもあったということだけは覚えている。
だが、料理のことよりも、普段は野武士のようないかつい風貌の祖父が涙を流し、祖母は何かを話しかけては嗚咽していたことは鮮明に覚えている。私もへっつい(釜戸)の前にしゃがみ込み声を出して泣いた。
別れの朝が来た。祖父母は浜松駅まで送ってくれた。バス停で別れる予定であったが、私が祖父母の手をしっかりと握りしめていっこうに離す気配がないため、駅のホームまでついてきた。列車に乗り込む段になってようやく祖父母の手を離した。
列車に乗り込んでからも母にガラス窓を開けてもらい、列車が動き出してからも「おばあちゃん。おじちゃん」と泣きながら大きな声で叫び続けた。
ほぼ三年ぶりに練馬にある我が家へ帰ってきたが、他人の家に来たようで落ち着かなかった.長年離れて暮らしていたため、兄弟ともすぐに打ち解けることができなかった。ただただ祖父母が恋しく、これから始まる新しい生活への不安ばかりが募った。
夕食は三年前とは代わり、ずいぶんと良くなっていた。夜になり、父親が帰宅した。「お帰り、大きくなったな。ホレ、アッ君へのお土産だ。チョコレートというんだぞ。甘くておいしいぞ、さ、食べてごらん」といって板チョコをくれた。
チョコを割り、ひとかけらを口に入れた。初めて体験する味であった。とても甘く、しかも苦みがある。その苦みが何とも言えず、甘みを引き立てている。これほどまでにおいしいものが東京にはあったというのは、子どもの私にとって強烈なショックであった。
終わらない戦争の傷跡
東京の家に戻り半年ほどが経った。子どもは環境に慣れるのが早い。家に戻った頃は掛塚の祖父母のことを思い出しては泣いたこともあったが、その頃になると、以前ほどの恋しさはなくなっていた。
焼け野原となり、焼け跡に作られた粗末なバラックの家はほとんど見かけなくなり、その頃には新しい家がたくさん建てられていた。殺気立っていた人々の表情も穏やかになっていた。
昭和二十四年四月、いよいよ小学校の入学式を迎えることになった。教科書はすでに母親が購入していた。ランドセル、学校で使う上履き、筆記用具などは入学式前に準備されていた。入学式に私の母も一緒に来たかどうかは覚えていないが、多分、一緒であったと思う。母親に手を引かれた私と同い年の新一年生がたくさんいた。
真新しい服も揃えてもらった。掛塚では真夏以外は膝くらいまでしかない絣の着物をいつも着ていたが、今は洋服である。上着の左胸には平仮名で名前を書いた白く大きなハンカチが、これまた大きな安全ピンで胸のポケットに付けられていた。履物もワラジではなく運動靴である。頭にはだぶだぶの黒い学生帽子が乗っかっていた。手には教室で履く上履きを入れた袋(通称、草履袋)を下げ、背中には教科書、ノート、筆箱の入ったランドセルを背負っていた。
すべてが新鮮であった。あれほど恋しかった掛塚のことなど、すっかり忘れ、これから始まる新しい学校生活への夢が膨らんでいった。
すべてが新しいとはいっても、ランドセルも筆記用具も実に粗末なものであった。ランドセルは紙で作られていた。厚手のボール紙に布を張ったもので、男の子は黒、女の子は赤の二種類しかなかった。一年もたつと肩掛けのところが切れてしまい、壊れるたびにかばん屋さんへ行き、修理してもらった。革製のランドセルは、私が三年生になった頃になって、やっと発売されたと記憶している。
筆記用具もかなりお粗末であった。鉛筆は芯がよく折れた。そのため、鉛筆削りは必携品であった。その鉛筆削りも二つ折りした細長い板状の金属の先の部分にカミソリの刃をはさんだだけのナイフか小刀である。鉛筆を削っているときにケガをする子もいた。鉛筆を削り、芯が顔を出したところで芯を引っ張ると芯だけが抜けてくることも多かった。三菱、トンボ、コーリンといったメーカーがあったが、いずれも同じような品質であった。
クレヨンもよく折れた。巻いてある紙をめくりながら使うのだが、よく手にクレヨンの色がついた。メーカーはサクラくれよんであった。
筆箱はセルロイド製のものが多く、蓋が割れやすかった。長辺のほぼ真ん中部分で真っ二つに割れるため、修理もしやすかった。割れた部分に沿って、その内側に、火をつけた線香で穴をあけていく。その穴へタコ糸を通して縛り付けるだけである。また、一閑張りのものもあった。ただし、伝統的民芸品のように和紙と漆で作られた高級なものではない。筆箱の形をした木型の上から古新聞などを貼り、色を付けて膠で固めたものだ。
いずれも安っぽく、すぐに壊れてしまうようなものばかりではあったが、ランドセルや筆記用具などを揃えられる子は幸せな方であった。
新一年生の中には戦争で両親を亡くした戦災孤児と呼ばれる子供たちがいた。彼らは保護施設から通っていたが、教科書などは風呂敷に包んでいた。
入学式は学校の運動場で行われた。全校児童の数は千人もの大所帯であった。学校の一日は運動場に全児童が並び、朝礼から始まる。正面には国旗と校旗が掲揚され、全員で校歌を斉唱した。こうしたことは私が三年生になった昭和二十六年に校長先生が移動するまで行われた。ただし、私が五年生になった昭和二十八年に体育館ができるまで、雨の日の朝礼は行われなかった.
一月一日は冬休み中であったが全員が午前十時までに登校し、朝礼が行われた。最初に国旗、校旗が掲揚され、国歌、校歌に続き「年の初めの ためしとて」の歌詞で始まる「一月一日(いちげつ いちじつ)」を斉唱した。最後に校長先生が挨拶をして朝礼は終わる。その後、各クラスごとに教室へ入り、担任の先生が挨拶し、のし紙に包まれた紅白の餅が配られ、昼前には帰宅した。
GHQは国旗掲揚を禁止していたが、私の入学した昭和二十四年に許可されたという。
私と同じ年に入学した児童の中には戦争で親を亡くし、片親の再婚や養子になるなどして入学してから姓が変わる子や養子になって転校していった子が、何人かいた。
さらに、戦地で捕虜として収容されていたが復員して、再び教壇に立つことになった先生も毎年一人か二人おられた。昭和二十七年ごろからは姓の変わる子や復員してくる先生も減っていったようだ。 戦争が終わって六年も過ぎていたのに、戦後は続いていたのである。
あとがき
私の姓は福井だが、父の旧姓は前原である。父が福井家に養子として入ったためである。しかし、母の子供時代の姓は朝比奈であった。ところが、母が子どもの時に、父である朝比奈新平が関東大震災後の心労によって亡くなり、祖母は福井作平と再婚した。祖母が再婚をしなかったならば、私の姓は朝比奈になっていたかもしれない。父が養子という形で結婚をしなければ、私は前原の姓になっていたかもしれない。朝比奈家も福井家も、それぞれの歴史を持っている、
朝比奈家は江戸時代は幕府の旗本であったという。そして浜松に知行地を賜っていた。しかし明治となり、江戸の屋敷を引き払い、現在の浜松市内に居を移し、さらに分家二家を作ったといわれている。朝比奈新平の実弟は浜松に住んでいたが、この人も養子として小栗姓となった。
福井の本家は明治三十一年の戸籍謄本を見ると、千葉県安房郡船形町舟形四七一番地となっている。ここに那古船形という湊があり、そこで江戸と結ぶ廻船問屋を営んでいた。江戸京橋にも店を持ち、かなり繁盛していたという。
しかし幕末になると、幕府側と反幕府側との間でさまざまな騒動が起き、そのあおりを受け、江戸店は焼打ちに遭った。千葉にあった本店は幸いにも被害をまぬがれ、明治になってからも何とか店を再建するための努力をしていた。やがて鉄道が敷かれ、廻船業は衰退していく。大正元年に鉄道が木更津まで伸び内房線として発展し、ついに廻船業は一気に廃業の道へと進んでいった。
私の祖父となった福井作平は、激動の世を生き抜いてきた福井家の婿養子として‘きち’と結婚し、東京都京橋区京橋に居を構えることになったが、昭和二年十月に “きち”と死別する。私の祖母である“その”も大正十二年九月一日の関東大震災の一年後に夫であった朝日奈新平と死別した。作平と“その”は昭和五年に再婚する。作平は “きち”との間にも“その”との間にも子供はできなかった。
“その”と作平は昭和二十五年に掛塚から東京へ戻ってきた。“その”は昭和二十五年に病死、作平は昭和三十二年に老衰のため永眠した。私と祖父・作平は直接的な血のつながりはないが、実の孫のように可愛がってくれた。
祖父と祖母は明治、大正、昭和という大きなうねりの時代の中を生き抜いた。母もまた関東大震災、太平洋戦争という激動の時代を生きた。昭和十七年生まれの私は両親や祖父母のように直接的な戦争の悲惨さを知らない。それでも、戦後の飢えに苦しめられた経験は覚えている。日々の食料もまともに手に入れることのできない中、よくぞ生きてこられたものだと思わざるを得ない。
昭和二十七年頃まで「千葉のおばちゃん」と呼んでいた小太りで大柄な女性が毎月、私の家を訪れていた。千葉県のどこからきているのかは知らないが、そのおばちゃんが来るのを私はいつも楽しみにしていた。
この女性と初めてあった時の驚きは今も覚えている。それは私が小学校二年生の昭和二十五年であった。
両手には葉物の野菜を入れた籐で編んだ買い物カゴを持ち、それを玄関の上がり端に置き母としばらく話をしていたかと思うと、いきなり着物の帯を解き、下着姿となった。よく見ると、下着を縛っているのは紐ではなく帯である。正確に言うと、帯と同じ幅の袋であった。その袋状の帯も取る。もちろん、下着はちゃんと紐で縛ってある。
袋状の帯は糸で縫って三つに区切られ、一区切りに米が一升、合計三升の米が入っていた。千葉のおばちゃんはヤミ米の行商人だったのだ。ヤミ米の行商人と聞くと、裏社会とつながった恐い人のような印象を受けるかもしれないが、決してそうではない。どこにでもいる、普通の善良な市民であった。
当時は主食である米は配給制のままであった。そのためヤミで米を販売すると、食糧管理法違反に問われたが、法律を遵守してヤミ市での購入をせず、配給だけで生活しようとすると、餓死する可能性があった。事実、昭和二十二年に東京地方裁判所の判事がヤミ市での食料購入を拒否し、栄養失調で死亡するという衝撃的な事件があった。つまり、法律は国民を守るものではなく、死へと追いやるためのものとなっていた。
おばちゃんが手にしていた野菜の入ったカゴはヤミ米を取り締まる警察官の目をごまかすカモフラージュのいわば小道具であった。その野菜を時にはお土産としておいて行ったたこともあったようだ。
昭和三十年頃、ラジオから流れる落語でよく使われた枕(マクラ)に「日本で一番よくお米のとれるのはどこか? それは赤羽である」というのがあった。獲れると捕れるをかけたのだ。当時はまだ、ヤミ米が東京にたくさん流入し、東北本線で東京に入って最初の乗り換え駅が赤羽であった。そのため、取り締まりが特に厳しかった。
米が自主流通米としてスーパーマーケットなどで売られるようになったのは昭和四十四年(一九六九)になってからである。
明治から百五十年、昭和二十年までの七十数年の間、日本は日清、日露、日中、太平洋戦争と、幾度も戦争を行ってきた。昭和二十年から平成の七十数年は、日本が直接戦争をすることはなかった。昭和と平成から一文字ずつを取れば「平和」となる。
私は今年で喜寿となる。私が生きてきた時代はまさに「平和」の時代であった。今、平成の時代が幕を閉じようとしているが、平和な時代だけは幕を閉じず、これからも続いていくことを心から願いたい。
平成三十一年四月三十日 福井 章

 福祉系情報誌の編集は得意分野です。日常持ち合わせている情報やネットワークを生かし、企画・取材・執筆・編集承っております。
福祉系情報誌の編集は得意分野です。日常持ち合わせている情報やネットワークを生かし、企画・取材・執筆・編集承っております。