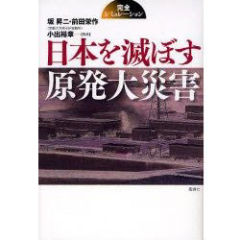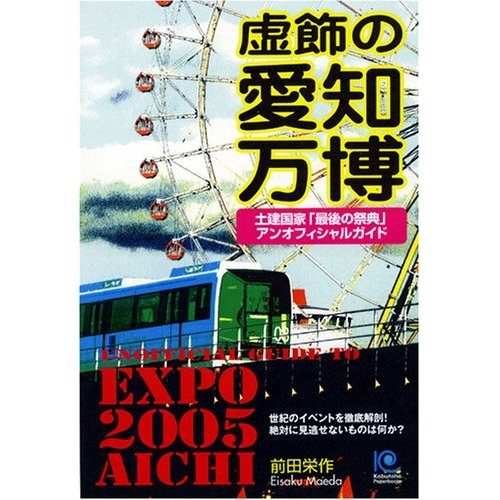「昭和十七年生まれがいなくなったなら……」<ワラジ・戦争の悲劇・お汁粉>福井 章著
 ワラジ
ワラジ
二人が風呂から帰ると、祖父はワラジづくりに精を出している。今では日常のあらゆるものを店や通販で購入できるが、昭和二十年代は日常的に使うものの多くが自家製であった。食べ物であれば白菜や大根の漬物、梅干し、さらには味噌も各家庭で作っていた。
普段着るものも手作りのものが多かった。主婦であれば和裁や編み物ができて当たり前であった。古着をほどいて子どもの着物を縫い直したり、毛糸でセーターを編んだり、中には手袋を編む人もいた。
履物も手作りされることが多かった。履物とはいっても、運動靴などではない。田舎の日常的な履物といえば稲わらで編んだワラジであった。
農家にはワラジの材料となる稲わらがいくらでもある。稲わらを木槌でたたいて柔らかくする。それを細い縄状に編む。その縄をワラジに編むのだが、機械は一切使わない。すべて手作業である。
長さと太さの揃った何本かの稲わらの端を結び、それを足の指にかける。それを三つの束に小分けし、両手で撚りながら三つ編みを結ぶ要領で編んでいく。端の方まで来たら稲わらを足して撚り込む。上手に編んでいかないと縄の太さが不揃いになってしまう。こうした作業を繰り返し、均一な太さの縄を作る。それからワラジを作る。鼻緒の部分は保管してある古着などを利用する。
しっかりと編み込んでないワラジは履いてもすぐにぼろぼろになってしまう。しっかり編み込んであっても、しょせんは藁で作られたものである。一日中履いていれば擦り切れて使えなくなる。特に農作業などで使えば、毎日履き替えなければならない。
畑は家から三十分ほど歩いたところと天竜川の中州の二か所にあった。中州にある畑へ行くには土手を超え、子どものくるぶしほどの浅瀬をじゃぶじゃぶ渡る。ワラジは土の斜面や水の中でも滑りにくい。祖父の作ったワラジを履いて、祖母と毎日のように出かけ、遊びを兼ねて畑仕事の手伝いをしたりした。水遊びをしたり、アマジの根を掘ってかじるのが楽しかった。
戦争の悲劇
掛塚の祖父母の家に来てから三か月ほど過ぎた。栄養失調で今にも死ぬかもしれないと思われていた私であったが、すっかり元気を取り戻し、畑の手伝いをしたり、天竜川の河原を楽しく飛び回れるようになっていた。
祖母の最初の夫である朝比奈新平は関東大震災後の心労がたたり、二人の娘を残して亡くなり、祖母は福井と再婚した。朝比奈家の本家は浜松市内にあり、朝比奈新平の姉が朝比奈家を継いでいた。私は新平の血を受け継いだ孫にあたる。秋も深まったある日、祖母は、元気になった私を連れて朝比奈の実家へ挨拶にいくことにした。
浜松市内も空襲で焼け野原となったが朝比奈の屋敷は幸いにも空襲などの被害に遭うことはなかった。二人は立派な床の間のある座敷へ通された。応対した女性は朝比奈新平の姉にあたる人であった。祖母が私の少し斜め後ろに座り「章です。四歳になりました」といって私を紹介した。
二人の間でどんな会話が交わされていたのか、子どもであった私は覚えていない。話が一段落したところで「どうぞこちらへ」といって仏間に案内された。昼間だというのに、仏間は薄暗かった。最初に私の目に飛び込んだのは仏壇ではなく、仏間の片隅で壁に向かったまま正座している若い男性の姿であった。私たちが仏間へ入っても、一言も声を発せず、ただじっと座っているだけであった。
この男性のことは祖母も何も知らなかったようだ。応対してくれた女性は涙を流しながら、祖母に何かを語っていた。その男性が母とどういった関係にあたる人なのかはわからないが、とにかく朝比奈家の一員であることだけは確かである。
後で祖母から聞かされた話によると、その男性は徴兵されて外地へ行った。どこでどのような体験をしたのか定かではないが、とにかくあのような姿で帰ってきたという。
最後に「お前が大人になっても兵隊だけにはなっちゃいけないよ。とにかく、どんな理由があるにせよ、戦争は絶対にしちゃいけないよ」とポツリと語った。
お汁粉
秋の日は釣瓶落としとはよく言ったものだ。浜松市内にある朝比奈家の家を後にする頃には、すでに夕闇が迫り、辺りは薄暗くなっていた。町中とはいっても街路灯はほとんどなく、ましてや明るく照らし出される広告塔もない。お店や各家庭の窓から漏れる白熱灯のボーとした薄明かりだけである。あっという間に暗闇に包まれていくのは、子どもにとって何とも言えない寂しさや怖さがある。
浜松駅前のバス乗り場まで歩いて来たが、バスの時間まではだいぶ時間があった。祖母が、お腹すいたかい、何か食べていこう、といって裸電球のぶら下がった店に入った。店内はうす暗かったが、外の闇のような世界に比べほっとできる場所であった。
店はすいていた。テーブルはどれもきれいとは言えなかった。メニューはいくつかあったのか、一つしかなかったのかはわからないが、祖母はお汁粉を二つ注文した。しばらく待っていると、湯気を立てたお汁粉が二つテーブルに運ばれてきた。二つとも同じ大きさであったのか、それとも一つは子供用であったのかもわからない。
いただきますというなり、器に口をつけてすすろうとした時、熱くて火傷するといけないから、ふーふーして冷ますんだよ、といわれた。これが生まれて初めて食べたお汁粉であったような気がする。一口すすると、口の中一杯に得も言われぬ甘さが広がった。今の今まで、これほど甘いものを食べたことはなかった。天竜川の土手でほじって噛んだアマジも甘かった。ほそばの実はもっと甘かった。しかし、それらとは比べ物にならないくらい甘くておいしかった。
当時の日本人は甘いものに飢えていた。甘いという言葉は同時においしいと同じ意味にも使われていた。砂糖は高級品であった時代である。砂糖の代わりにサッカリンとかズルチンと呼ばれる合成甘味料が使われていた。この時に食べたお汁粉も、おそらくサッカリンか何かで甘くしていたのだろう。それでもこの時に食べたお汁粉は最高の味で、いまだこの時のようにおいしいお汁粉には出会ったことがない。
・・・・・<死んだはずの人が歩いている・偶然の結果・初めて見たおもちゃの自動車>へつづく

 福祉系情報誌の編集は得意分野です。日常持ち合わせている情報やネットワークを生かし、企画・取材・執筆・編集承っております。
福祉系情報誌の編集は得意分野です。日常持ち合わせている情報やネットワークを生かし、企画・取材・執筆・編集承っております。