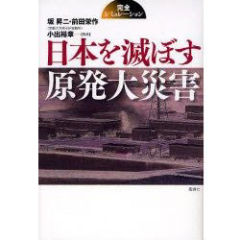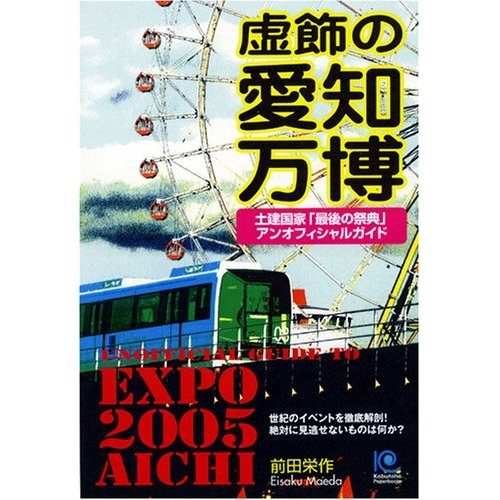「昭和十七年生まれがいなくなったなら……」<死んだはずの人が歩いている・偶然の結果・初めて見たおもちゃの自動車>福井 章著
 死んだはずの人が歩いている
死んだはずの人が歩いている
掛塚には帝国館という大衆劇場があった。人々は食べるものに飢えていたが、娯楽にも飢えていた。ある日、農作業の暇になった時期に帝国館で旅の一座の芝居が行われることになった。祖父母がその芝居を見に行くことになった。もちろん私も連れて行ってもらえた。
どんな演目であったのかは全く覚えていないが、浜松という土地柄から、清水の次郎長が演じられたのではないかと思う。当事、GHQによって、チャンバラ映画は禁じられていた。この措置は昭和二十七年まで続いた。だが、舞台演劇でのチャンバラは禁止にはなっていなかった。
そのため、剣劇はどこへ行っても大いに盛り上がった。主人公が相手をバッタバッタと切り倒す度に会場からは大きな拍手が巻き起こった。幼い子供の私でも、手に汗を握り胸のすくのを覚えた。鬱屈した時代の中にあって、人々はなんとも言えない爽快感を覚えたのだろう。
次の場面へと移るため、舞台の照明が落とされた。準備のため、一瞬、舞台の照明が点いた。その時である。舞台横を歩いている一人の人物を見た私は、思わず「ウワァー」と素っ頓狂な声をあげて、祖父にしがみついた。先ほどの場面で切られて死んだはずの人が歩いていたのだ。舞台から目をそらし震えながらしがみつく私に、祖父は何事かと驚き「どうした」と聞いた。「おじいちゃんあそこ、あそこをさっき切られた人が歩いていたよ」と半ば震える声で答えた。祖父の声が急に柔らかくなり「そうか、そうか。これはお芝居だから、本当に切られて死んだわけではないんだよ」と私の耳元で囁くように話してくれた。それを聞いて、半分は納得したが完全に理解できたわけではない。それでも、楽しい一時を過ごすことができた。
偶然の結果
祖母には妹がいた。その人は遠州灘に近い駒場というところに住んでいた。祖母と私はそのおばさん夫婦の家に遊びに行ったことがある。
おばさんは若いころ、なかなかの美人であった。朝比奈新平が祖母と結婚したいきさつはちょっとした勘違いからであったという。
当事、結婚相手は自分で探し出すのではなく、誰かに紹介してもらうのが当たり前であった。いわゆるお見合いである。それもお互いが会ってゆっくりと会話を交わし、気に入ったなら結婚を決めるというのではない。時にはお見合い写真も見ない。仲介人がそれぞれの家の親に、こんな人がいるがどうかと話を持ち掛ける。親同士が気に入れば婚約成立ということもあった。そこに結婚する本人の意思が働く余地はほとんどなかった。
新平に結婚話が持ち上がった。浜松市内の料亭で形ばかりのお見合いをすることになった。料亭の一室でその日の段取りを打ち合わせていると、こちらをちらちらと覗きながら美しい女性が庭を横切っていった。新平は一目で気に入って仲人さんに、結婚しますと即答してしまった。答えが出たので、その日の見合いは必要なくなった。結婚の日取りまでの段取りを打ち合わせて帰宅した。
さて、結婚式当日、陽が落ちてから式が始まった。式は滞りなく終えた。新郎、新婦は別室に入った。そこで新郎が花嫁の被っている綿帽子をそっと外す。その瞬間、新郎は「違う」と叫んだ。
浜松の料亭で見た女性とは別人だというわけだが、式は滞りなく終わっていた。別人であっても、今さらどうすることもできない。
実は新平が料亭で見たのは祖母の妹であった。姉の亭主となる人は自分にとっては兄になる人だ。いったいどんな人なのかが知りたくて、料亭の庭に忍び込んだのだ。新平はそれを自分の見合い相手だと勘違いしたのである。祖母は私の母に、「初めて交わした言葉が『違う』というのは、あんまりだよね。まるで私の器量が悪いみたいで失礼な話だよ」とよくこぼしていたという。
駒場に住んでいた祖母の妹に会った時、子供心にも、きれいな人だと感じた。後年、祖母が四十歳ころの写真を見たことがあるが、若いころの祖母もなかなかの美人であったと思う。
初めて見たおもちゃの自動車
掛塚の祖父母の家に来て、約一年半が経った昭和二十一年の暮れ、両親と兄、二歳年下の弟がそろってやって来た。その日は大晦日を翌日に控え、餅を搗き、ちょうど筵の上に並べているところであった。東京では搗き立てのひと臼分の餅を伸ばし、大きな長方形にする。それを切って四角い切り餅にするのだが、その日は搗いた餅をそのままこぶし大にちぎり、一つずつ丸めた。
両親は私にゼンマイ仕掛けの自動車のおもちゃをお土産として持ってきてくれた。それまで、私の遊び場といえば、畑であり、川であり、家の周辺などで、トンボ、イナゴ、バッタ、蝶、ドジョウ、カエル、タニシ、家で飼っているニワトリなどをおもちゃとして遊んでいた。燃料にするため祖母と一緒に出かける天竜川の河原の石ころや拾い集める焚き木も私にとってはおもちゃであった。自然以外のおもちゃというものを手にしたことも見たこともなかった。
両親が持ってきてくれた小さな本物そっくりの自動車、しかもゼンマイで動くおもちゃ。最初はゼンマイで動くということもわからず、ひっくり返すなどしてただただ珍しがっていた。そのうちに、兄がゼンマイを巻いて走らせた。それを見て、またまたびっくりし、四つん這いになっておもちゃの自動車を追いかけた。兄からゼンマイの巻き方を教えられ、無我夢中で部屋の中を走らせ、必死になって追いかけまわした。
そんな私の嬉しそうな姿を見て、祖父母も両親も笑い声をたてて喜んだ。何年かぶりの家族全員での笑い声があった。
・・・・・<たった一度の祖父母の喧嘩・暴れる天竜川>へつづく
「昭和十七年生まれがいなくなったなら……」<ワラジ・戦争の悲劇・お汁粉>福井 章著
 ワラジ
ワラジ
二人が風呂から帰ると、祖父はワラジづくりに精を出している。今では日常のあらゆるものを店や通販で購入できるが、昭和二十年代は日常的に使うものの多くが自家製であった。食べ物であれば白菜や大根の漬物、梅干し、さらには味噌も各家庭で作っていた。
普段着るものも手作りのものが多かった。主婦であれば和裁や編み物ができて当たり前であった。古着をほどいて子どもの着物を縫い直したり、毛糸でセーターを編んだり、中には手袋を編む人もいた。
履物も手作りされることが多かった。履物とはいっても、運動靴などではない。田舎の日常的な履物といえば稲わらで編んだワラジであった。
農家にはワラジの材料となる稲わらがいくらでもある。稲わらを木槌でたたいて柔らかくする。それを細い縄状に編む。その縄をワラジに編むのだが、機械は一切使わない。すべて手作業である。
長さと太さの揃った何本かの稲わらの端を結び、それを足の指にかける。それを三つの束に小分けし、両手で撚りながら三つ編みを結ぶ要領で編んでいく。端の方まで来たら稲わらを足して撚り込む。上手に編んでいかないと縄の太さが不揃いになってしまう。こうした作業を繰り返し、均一な太さの縄を作る。それからワラジを作る。鼻緒の部分は保管してある古着などを利用する。
しっかりと編み込んでないワラジは履いてもすぐにぼろぼろになってしまう。しっかり編み込んであっても、しょせんは藁で作られたものである。一日中履いていれば擦り切れて使えなくなる。特に農作業などで使えば、毎日履き替えなければならない。
畑は家から三十分ほど歩いたところと天竜川の中州の二か所にあった。中州にある畑へ行くには土手を超え、子どものくるぶしほどの浅瀬をじゃぶじゃぶ渡る。ワラジは土の斜面や水の中でも滑りにくい。祖父の作ったワラジを履いて、祖母と毎日のように出かけ、遊びを兼ねて畑仕事の手伝いをしたりした。水遊びをしたり、アマジの根を掘ってかじるのが楽しかった。
戦争の悲劇
掛塚の祖父母の家に来てから三か月ほど過ぎた。栄養失調で今にも死ぬかもしれないと思われていた私であったが、すっかり元気を取り戻し、畑の手伝いをしたり、天竜川の河原を楽しく飛び回れるようになっていた。
祖母の最初の夫である朝比奈新平は関東大震災後の心労がたたり、二人の娘を残して亡くなり、祖母は福井と再婚した。朝比奈家の本家は浜松市内にあり、朝比奈新平の姉が朝比奈家を継いでいた。私は新平の血を受け継いだ孫にあたる。秋も深まったある日、祖母は、元気になった私を連れて朝比奈の実家へ挨拶にいくことにした。
浜松市内も空襲で焼け野原となったが朝比奈の屋敷は幸いにも空襲などの被害に遭うことはなかった。二人は立派な床の間のある座敷へ通された。応対した女性は朝比奈新平の姉にあたる人であった。祖母が私の少し斜め後ろに座り「章です。四歳になりました」といって私を紹介した。
二人の間でどんな会話が交わされていたのか、子どもであった私は覚えていない。話が一段落したところで「どうぞこちらへ」といって仏間に案内された。昼間だというのに、仏間は薄暗かった。最初に私の目に飛び込んだのは仏壇ではなく、仏間の片隅で壁に向かったまま正座している若い男性の姿であった。私たちが仏間へ入っても、一言も声を発せず、ただじっと座っているだけであった。
この男性のことは祖母も何も知らなかったようだ。応対してくれた女性は涙を流しながら、祖母に何かを語っていた。その男性が母とどういった関係にあたる人なのかはわからないが、とにかく朝比奈家の一員であることだけは確かである。
後で祖母から聞かされた話によると、その男性は徴兵されて外地へ行った。どこでどのような体験をしたのか定かではないが、とにかくあのような姿で帰ってきたという。
最後に「お前が大人になっても兵隊だけにはなっちゃいけないよ。とにかく、どんな理由があるにせよ、戦争は絶対にしちゃいけないよ」とポツリと語った。
お汁粉
秋の日は釣瓶落としとはよく言ったものだ。浜松市内にある朝比奈家の家を後にする頃には、すでに夕闇が迫り、辺りは薄暗くなっていた。町中とはいっても街路灯はほとんどなく、ましてや明るく照らし出される広告塔もない。お店や各家庭の窓から漏れる白熱灯のボーとした薄明かりだけである。あっという間に暗闇に包まれていくのは、子どもにとって何とも言えない寂しさや怖さがある。
浜松駅前のバス乗り場まで歩いて来たが、バスの時間まではだいぶ時間があった。祖母が、お腹すいたかい、何か食べていこう、といって裸電球のぶら下がった店に入った。店内はうす暗かったが、外の闇のような世界に比べほっとできる場所であった。
店はすいていた。テーブルはどれもきれいとは言えなかった。メニューはいくつかあったのか、一つしかなかったのかはわからないが、祖母はお汁粉を二つ注文した。しばらく待っていると、湯気を立てたお汁粉が二つテーブルに運ばれてきた。二つとも同じ大きさであったのか、それとも一つは子供用であったのかもわからない。
いただきますというなり、器に口をつけてすすろうとした時、熱くて火傷するといけないから、ふーふーして冷ますんだよ、といわれた。これが生まれて初めて食べたお汁粉であったような気がする。一口すすると、口の中一杯に得も言われぬ甘さが広がった。今の今まで、これほど甘いものを食べたことはなかった。天竜川の土手でほじって噛んだアマジも甘かった。ほそばの実はもっと甘かった。しかし、それらとは比べ物にならないくらい甘くておいしかった。
当時の日本人は甘いものに飢えていた。甘いという言葉は同時においしいと同じ意味にも使われていた。砂糖は高級品であった時代である。砂糖の代わりにサッカリンとかズルチンと呼ばれる合成甘味料が使われていた。この時に食べたお汁粉も、おそらくサッカリンか何かで甘くしていたのだろう。それでもこの時に食べたお汁粉は最高の味で、いまだこの時のようにおいしいお汁粉には出会ったことがない。
・・・・・<死んだはずの人が歩いている・偶然の結果・初めて見たおもちゃの自動車>へつづく
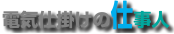
 福祉系情報誌の編集は得意分野です。日常持ち合わせている情報やネットワークを生かし、企画・取材・執筆・編集承っております。
福祉系情報誌の編集は得意分野です。日常持ち合わせている情報やネットワークを生かし、企画・取材・執筆・編集承っております。
 次へ ≫
次へ ≫