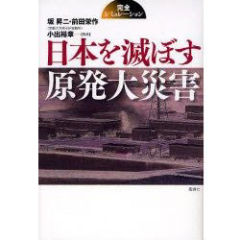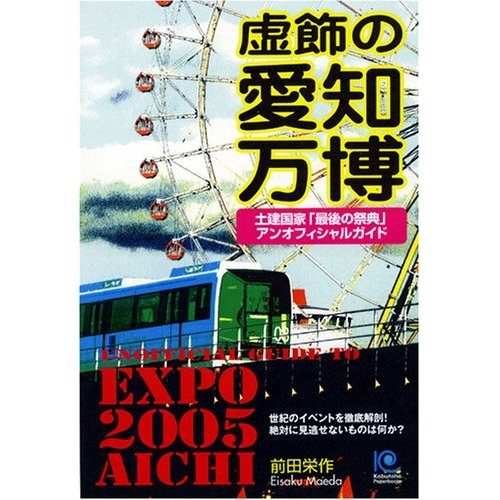гҖҢжҳӯе’ҢеҚҒдёғе№ҙз”ҹгҒҫгӮҢгҒҢгҒ„гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒӘгӮүвҖҰвҖҰгҖҚпјң家ж—ҸгҒЁеҲҘгӮҢйқҷеІЎгҒёгғ»гҒҠгҒ«гҒҺгӮҠгғ»дҪ•гҒӢжңҲгҒ¶гӮҠгҒӢгҒ®гҒҠзұігҒ®гҒ”йЈҜпјһзҰҸдә• з« и‘—
 家ж—ҸгҒЁеҲҘгӮҢйқҷеІЎгҒё
家ж—ҸгҒЁеҲҘгӮҢйқҷеІЎгҒё
з§ҒгҒҢеҸ°жүҖгҒ§еҖ’гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹзҝҢжңқгҖҒйқҷеІЎгҒёеҮәзҷәгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®ж—ҘгҒҜжңқгҒӢгӮүйӣІдёҖгҒӨгҒӘгҒ„еҝ«жҷҙгҒ§гҒЁгҒҰгӮӮжҡ‘гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮжңқж—©гҒҸжҜҚиҰӘгҒ«иө·гҒ“гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
гҒ„гҒӨгӮӮгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е°‘гҒ—гҒ гҒ‘з Ӯзі–гӮ’е…ҘгӮҢгҒҹиҢ¶зў—гҒ«ж№ҜгӮ’жіЁгҒҺгҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒёеүҚж—ҘгҒ«жҜҚиҰӘгҒҢй…ҚзөҰгҒ§иІ·гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹд№ҫгғ‘гғігӮ’жөёгҒ—гҖҒгҒөгӮ„гҒ‘гҒҰжҹ”гӮүгҒӢгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹй ғгӮ’иҰӢиЁҲгӮүгҒЈгҒҰйЈҹгҒ№гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҢгҒқгҒ®ж—ҘгҒ®жңқйЈҹгҒ®гҒҷгҒ№гҒҰгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжңқйЈҹгӮ’йЈҹгҒ№зөӮгҒҲгӮӢгҒЁдј‘гӮҖй–“гӮӮгҒӘгҒҸжҖҘгҒ„гҒ§еҮәзҷәгҒ®жә–еӮҷгӮ’гҒ—гҒҰжқұдә¬й§…гҒёгҒЁеҗ‘гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
зҲ¶гҒҜеҲҮз¬ҰгҒ®жүӢй…ҚгӮ’гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгӮҲгӮҠдёҖи¶іж—©гҒҸжқұдә¬й§…гҒёеҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮдәҢжӯігҒ®ејҹгӮ’гҒҠгӮ“гҒ¶гҒ—гҒҹжҜҚгҒ«жүӢгӮ’еј•гҒӢгӮҢгҖҒзҲ¶гҒ®еҫҢгӮ’иҝҪгҒЈгҒҹгҖӮ
й§…гҒ®гғӣгғјгғ гҒҜгҒҷгҒ”гҒ„дәәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮзҷҪгҒ„и’ёж°—гӮ’еҗҗгҒҚгҖҒй»’гҒ„з…ҷгӮ’еҮәгҒҷи’ёж°—ж©ҹй–ўи»ҠгҒҜе·ЁеӨ§гҒӘйү„гҒ®еЎҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮ„гҒҢгҒҰгҒ‘гҒҹгҒҹгҒҫгҒ—гҒ„жұҪз¬ӣгҒҢйіҙгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гӮ¬гғғгӮҜгғігҒЁгҒ„гҒҶиЎқж’ғгӮ’ж„ҹгҒҳгҖҒжұҪи»ҠгҒҜгӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁеӢ•гҒҚеҮәгҒ—гҒҹгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜеә§еёӯгӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒҢгҖҒеә§гӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹдәәгҒҜеӨ§гҒҚгҒӘгғҲгғ©гғігӮҜгӮ„гғӘгғҘгғғгӮҜгӮөгғғгӮҜгӮ’йҖҡи·ҜгҒ®еәҠгҒ«зҪ®гҒҚгҖҒгҒқгӮҢгӮ’еә§еёӯд»ЈгӮҸгӮҠгҒ«еә§гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮдёӯгҒ«гҒҜдәәгҒҢеә§гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеә§еёӯгҒ®иӮҳжҺӣгҒ‘гӮ’еә§еёӯжӣҝгӮҸгӮҠгҒ«дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәәгӮӮгҒ„гҒҹгҖӮ
гҒ„гҒӨгҒ—гҒӢз§ҒгҒҜзң гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮжҳјиҝ‘гҒҸгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒжұҪи»ҠгҒҜгӮҲгҒҶгӮ„гҒҸйқҷеІЎй§…гҒ«зқҖгҒ„гҒҹгҖӮеӨ§гҒҚгҒӘйғҪеёӮгҒ®й§…гҒ гҒ‘гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒд№—гӮҠйҷҚгӮҠгҒҷгӮӢдәәгҒ®ж•°гӮӮеӨҡгҒ„гҖҒгҒҹгҒ гҒ§гҒ•гҒҲж··йӣ‘гҒ—гҒҹи»ҠеҶ…гӮ’еӨ§гҒҚгҒӘиҚ·зү©гӮ’жҢҒгҒЈгҒҹдәәгҒҹгҒЎгҒҢеҮәе…ҘгӮҠгҒҷгӮӢгҖӮеә§гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәәгҒ«иҚ·зү©гҒҢеҪ“гҒҹгӮӢгҖӮгҒқгҒ®еәҰгҒ«гҖҢз—ӣгҒ„гҖҚгҒ гҒ®гҖҒгҖҢж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гӮҚгҖҚгҖҒгҖҢгҒқгҒ“гҖҒгҒ©гҒ„гҒҰгҒҸгӮҢгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁжҖ’йіҙгӮӢдәәгӮӮгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒқгӮ“гҒӘйЁ’гҖ…гҒ—гҒ•гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒзң гӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹз§ҒгҒ®зӣ®гҒҢиҰҡгӮҒгҒҹгҖӮе–§йЁ’гҒҢдёҖж®өиҗҪгҒ—гҒҹй ғгҖҒжұҪи»ҠгҒҜеҶҚгҒіжұҪз¬ӣгӮ’йіҙгӮүгҒ—гҒҰеӢ•гҒҚе§ӢгӮҒгҒҹгҖӮйқҷеІЎй§…гҒ§гҒҜз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®еүҚгҒ®еёӯгҒ«дёӯе№ҙгҒ®еҘіжҖ§гҒЁз”·жҖ§гҒҢеә§гҒЈгҒҹгҖӮеҘіжҖ§гҒҜжүӢгҒ«гҒ—гҒҹиҚ·зү©гӮ’з¶ІжЈҡгҒ«зҪ®гҒҚгҖҒгҒқгҒ®жЁӘгҒ«гҖҒз”·жҖ§гҒҢиҚ·зү©гӮ’зҪ®гҒ„гҒҹгҖӮ
гҒҠгҒ«гҒҺгӮҠ
гӮ„гҒҢгҒҰжұҪи»ҠгҒҜе®үйғЁе·қйү„ж©ӢгӮ’жёЎгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬еқӮгғҲгғігғҚгғ«гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгҖӮеҪ“жҷӮгҒ®жұҪи»ҠгҒ«еҶ·жҲҝгҒӘгҒ©гҒӘгҒ„гҖӮжҡ‘гҒ„ж—ҘгҒҜзӘ“гӮ’й–ӢгҒ‘гҖҒйўЁгҒҢе…ҘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғҲгғігғҚгғ«гҒ®дёӯгҒ§гҒҜзҹізӮӯгҒ®з…ҷгҒҢй–ӢгҒ„гҒҹзӘ“гҒӢгӮүи»ҠеҶ…гҒ«е…ҘгӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҒҸгӮӢгҖӮжҡ‘гҒ•гӮ’жҲ‘ж…ўгҒ—гҒҰзӘ“гӮ’й–үгӮҒгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„гҖӮ
гӮ„гҒЈгҒЁгғҲгғігғҚгғ«гӮ’жҠңгҒ‘и»ҠеҶ…гҒҢжҳҺгӮӢгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒзӘ“гӮӮй–ӢгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§еҘіжҖ§гҒҜз¶ІжЈҡгҒ®иҚ·зү©гӮ’дёӢгӮҚгҒ—гҖҒдёӯгҒӢгӮүгҒҠгҒ«гҒҺгӮҠгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҹгҖӮеӨ§гҒҚгҒ•гҒҜеӣӣжӯігҒ®з§ҒгҒ®йЎ”гҒ»гҒ©гҒ«гӮӮиҰӢгҒҲгҒҹгҖӮгҒқгӮ“гҒӘгҒҠгҒ«гҒҺгӮҠгҒ®дёҖгҒӨгӮ’з„ЎйҖ дҪңгҒ«гҒ»гҒҠгҒ°гҒЈгҒҹгҖӮ
з„ЎиЁҖгҒ§еҘіжҖ§гҒ®д»•иҚүгӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гҒҹз§ҒгҒҜйқҙгӮ’и„ұгҒҺгҖҒзӘ“гҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰжӯЈеә§гҒ—гҒҰеӨ–гҒ®йўЁжҷҜгӮ’иҰӢгҒҹгҖӮгҒ—гҒ°гӮүгҒҸгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒжҜҚгҒҢгҖҢгӮўгғғеҗӣгҖӮгҒҠеӣЈеӯҗгӮ’йЈҹгҒ№гӮӢпјҹгҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹгҖӮз§ҒгҒҜгҖҢйЈҹгҒ№гҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒӨгӮҢгҒӘгҒҸиҝ”дәӢгӮ’иҝ”гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰжӯЈеә§гҒ—гҒҹгҒҫгҒҫзӘ“жһ гҒ®дёҠгҒ«д№—гҒӣгҒҹдёЎи…•гҒ«йЎ”гӮ’зҪ®гҒҚгҖҒи»ҠзӘ“гӮ’жөҒгӮҢгӮӢйўЁжҷҜгӮ’гҒјгӮ“гӮ„гӮҠгҒЁзңәгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
жҜҚгҒҢйЈҹгҒ№гҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁиҒһгҒ„гҒҹеӣЈеӯҗгҒҜеҺҡгҒҝзҙ„дёҖгӮ»гғігғҒгҖҒзӣҙеҫ„зҙ„дә”гӮ»гғігғҒгҒ§зҒ°иүІгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ©гӮ“гҒӘжқҗж–ҷгҒ§дҪңгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгӮігғЎгҒ§гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ гҒ‘гҒҜеӯҗдҫӣгҒ®з§ҒгҒ«гӮӮгӮҸгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒЁгҒҰгӮӮй…ёгҒЈгҒұгҒ„е‘ігҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁиЁҳжҶ¶гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзҸҫеңЁгҒӘгӮүгҖҒзҠ¬гҒ®йӨҢгҒ«гӮӮгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒҸгӮүгҒ„гҒҫгҒҡгҒ„д»Јзү©гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮ“гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гӮӮгҖҒиІ·гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°е№ёйҒӢгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ“гҒ®жҷӮгҒ®иЁҳжҶ¶гӮ’жҜҚгҒ«и©ұгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгҖҢгӮӮгҒ—гӮӮгҒҠеүҚгҒҢгҒҠгҒ«гҒҺгӮҠгӮ’йЈҹгҒ№гҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒӘгӮүгҖҒгҒӮгҒ®еҘіжҖ§гҒ«еңҹдёӢеә§гҒ—гҒҰгҒ§гӮӮе°‘гҒ—еҲҶгҒ‘гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖҒйЈҹгҒ№гҒӢгҒ‘гҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гӮӮзөҗж§ӢгҒ§гҒҷгҖӮгҒ„гҒҸгӮүеҮәгҒӣгҒ°еЈІгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҫгҒҷгҒӢгҒЁжҮҮйЎҳгҒҷгӮӢгҒӨгӮӮгӮҠгҒ гҒЈгҒҹгҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҒқгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжұҪи»ҠгҒҜз„ЎдәӢгҒ«жөңжқҫй§…гҒ«зқҖгҒ„гҒҹгҖӮзҘ–зҲ¶жҜҚгҒҢдҪҸгӮҖжҺӣеЎҡгҒёгҒҜжөңжқҫй§…гҒӢгӮүгғҗгӮ№гҒ«д№—гӮҠгҖҒеӨ©з«ңе·қжүӢеүҚгҒ®зөӮзӮ№гҒҫгҒ§иЎҢгҒҸгҖӮгҒқгҒ“гҒӢгӮүгҒ•гӮүгҒ«еҚҒдә”еҲҶгҒ»гҒ©жӯ©гҒ„гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҖӮ
гғҗгӮ№гӮ’йҷҚгӮҠгҖҒз§ҒгҒҜжҜҚгҒЁжүӢгӮ’гҒӨгҒӘгҒҺеӨ©з«ңе·қгҒ«жһ¶гҒӢгҒЈгҒҹжңЁгҒ§гҒ§гҒҚгҒҹж©ӢгӮ’жёЎгҒЈгҒҹгҖӮжҜҚгҒ®еҝғй…ҚгӮ’гӮҲгҒқгҒ«гҖҒз§ҒгҒҜзҹҘгӮүгҒӘгҒ„дё–з•ҢгҒёжқҘгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒзҲ¶жҜҚгӮ„е…„ејҹгҒЁеҲҘгӮҢгӮӢеҝғй…ҚгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒгҒ©гҒ“гҒӢжө®гҒҚжө®гҒҚгҒ—гҒҹж°—жҢҒгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ家гӮ’еҮәгҒҹжҷӮгҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжҺӣеЎҡгҒ®з©әгӮӮгӮҲгҒҸжҷҙгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
дҪ•гҒӢжңҲгҒ¶гӮҠгҒӢгҒ®гҒҠзұігҒ®гҒ”йЈҜ
гҖҢгҒҠжҜҚгҖҒгҒҠжҜҚгҖҚгҖӮжҜҚгҒҢеӨ§гҒҚгҒӘеЈ°гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҹгҖӮжҲёгҒҜз©әгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒ家гҒ®дёӯгҒӢгӮүгҒҜзү©йҹідёҖгҒӨиҒһгҒ“гҒҲгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮзҘ–зҲ¶жҜҚгҒҜз•‘д»•дәӢгҒ«еҮәгҒӢгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжҲёз· гӮҠгҒӘгҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒзҺ„й–ўгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒҢзёҒеҒҙгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒҢгҖҒ家гҒ®дёӯгҒёгҒҜгҒ©гҒ“гҒӢгӮүгҒ§гӮӮиҮӘз”ұгҒ«е…ҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ
жҺӣеЎҡгҒ®е®¶гҒҜгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁдёүгҖҮеқӘгҒҸгӮүгҒ„гҒ®еәғгҒ•гҒ®иҫІе®¶гҒ®зҙҚеұӢгӮ’еҖҹгӮҠгҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮгҒқгӮҢгӮ’зҘ–зҲ¶гҒҢж”№йҖ гҒ—гҒҰдҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҖӮ
зҘ–зҲ¶гҒҜи…•гҒ®гҒ„гҒ„еӨ§е·ҘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҢеәҠгҒ®й–“еӨ§е·ҘгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰеәҠгҒ®й–“гҒ®йғЁеұӢгҒ—гҒӢдҪңгҒЈгҒҰгҒ“гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ家гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜдҪңгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠеӨ§е·ҘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢгҒёгҒЈгҒӨгҒ„гҖҚпјҲйҮңжҲёпјүгӮ’йҖ гӮҠгҖҒеңҹй–“гҒЁдәҢгҖҮз•ігҒ»гҒ©гҒ®йғЁеұӢгҒЁзёҒеҒҙгӮ’йҖ дҪңгҒ—гҖҒиҰӢдәӢгҒӘдёҖ軒家гҒ«дҪңгӮҠжӣҝгҒҲгҒҹгҖӮеңҹй–“гҒ«гҒҜеҸҺз©«гҒ—гҒҹиҫІдҪңзү©гҒҢзҪ®гҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
家гҒ®е…ҘгӮҠеҸЈгӮ’е…ҘгӮӢгҒЁгҖҒе·ҰжүӢгҒҢдәҢгҖҮз•ігҒ»гҒ©гҒ®йғЁеұӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮйғЁеұӢгҒ«дёҠгҒҢгӮҠгҖҒжҠјгҒ—е…ҘгӮҢгҒӢгӮүеёғеӣЈгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҹжҜҚгҒҜгҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«иІ гҒ¶гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹејҹгӮ’дёӢгӮҚгҒ—гҒҰеҜқгҒӢгҒ—гҒӨгҒ‘гҒҹгҖӮеҲқгӮҒгҒҰиЁӘгӮҢгҒҹз§ҒгҒҜйғЁеұӢгҒ®дёӯгӮ’гҒҚгӮҮгӮҚгҒҚгӮҮгӮҚгҒЁиҰӢгҒҫгӮҸгҒ—гҒҹгҖӮгӮ„гҒҢгҒҰгҖҒгҒЎгӮғгҒ¶еҸ°гҒ®жЁӘгҒ«гҒӮгӮӢгҒҠж«ғгҒҢзӣ®гҒ«з•ҷгҒҫгӮӢгӮ„гҒ„гҒӘгӮ„гҖҒгҒҫгӮӢгҒ§е®қзү©гҒ§гӮӮиҰӢгҒӨгҒ‘гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«зӣ®гӮ’гӮ«гғғгҒЁиҰӢй–ӢгҒ„гҒҰй§ҶгҒ‘еҜ„гҒЈгҒҹгҖӮи“ӢгӮ’еҸ–гӮӢгҒЁгҖҒйәҰгҒ”гҒҜгӮ“гҒҢе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
жҳјжҷӮгҒ®жҷӮй–“гҒҜгҒӢгҒӘгӮҠйҒҺгҒҺгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸгҖҒзҘ–жҜҚгҒҢжҳјйЈҜз”ЁгҒ«жңқзӮҠгҒ„гҒҹгҒ”йЈҜгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ
гҖҢжҜҚгҒЎгӮғгӮ“гҒ”йЈҜгҒ гӮҲгҖҒгҒ”йЈҜгҒҢгҒӮгӮӢгӮҲгҖҚгҖӮжқұдә¬гҒ§гҒ®йЈҹгҒ№зү©гҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒгӮӨгғўгҖҒиұҶгҖҒеӨ§ж №гҖҒгҒҷгҒ„гҒЁгӮ“гҖҒеәӯгҒ®гҒӮгӮӢ家гҒҜе°ҸгҒ•гҒӘз•‘гӮ’гҒӨгҒҸгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒгӮӨгғҒгӮёгӮҜгҒӘгҒ©гҖҒе®ҹгҒ®гҒӘгӮӢжңЁгӮ’жӨҚгҒҲгҖҒгҒқгӮҢгҒ§йЈўгҒҲгӮ’гҒ—гҒ®гҒ„гҒ§гҒ„гҒҹгҖӮгҒҹгҒ гҒ§гҒ•гҒҲиҮӘеҲ¶еҝғгҒ®еҠ№гҒӢгҒӘгҒ„гҒ®гҒҢеӯҗгҒ©гӮӮгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгӮӮгҖҒгҒҠж«ғгҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгҒ”йЈҜгҒӘгҒ©гҖҒгҒ“гҒ“дҪ•гҒӢжңҲгӮӮгҒҠзӣ®гҒ«гҒӢгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮ
гҖҢгӮўгӮЎгғјгҖҚгҒЁгӮӮгҖҢгӮҰгӮ©гғјгҖҚгҒЁгӮӮгӮҸгҒ‘гҒ®гӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„иЁҖи‘үгӮ’зҷәгҒ—гҖҒгҒҠж«ғгҒ®дёӯгҒёжүӢгӮ’зӘҒгҒЈиҫјгӮ“гҒ§йәҰгҒ”гҒҜгӮ“гӮ’й·ІжҺҙгҒҝгҒ«гҒ—гҒҰжҜҚгҒ®йЎ”гҒ®еүҚгҒёзӘҒгҒҚеҮәгҒ—гҒҹгҖӮгҒ„гҒҸгӮүзҲ¶жҜҚгҒ®е®¶гҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҖҒйҖЈзөЎгӮӮгҒӣгҒҡгҒ«иЁӘгӮҢгҖҒеӢқжүӢгҒ«дёҠгҒҢгӮҠиҫјгҒҝгҖҒз„Ўж–ӯгҒ§гҒ”йЈҜгӮ’йЈҹгҒ№гӮӢгҒ®гҒҜзӨје„ҖгҒ«еҸҚгҒҷгӮӢгҒҜгҒҡгҒ гҒҢгҖҒгҒқгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒ«гҒҜгҒӢгҒҫгҒЈгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮжҜҚгҒ®и„іиЈЎгҒ«гҒҜгҖҒгҒӨгҒ„дёҖпҪһдәҢжҷӮй–“гҒ»гҒ©еүҚгҖҒеҲ—и»ҠгҒ®дёӯгҒ§гҒҠгҒ«гҒҺгӮҠгӮ’йЈҹгҒ№гҒҰгҒ„гҒҹеҘіжҖ§гӮ’иҰӢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«еҝ…жӯ»гҒ§з©әи…№гӮ’гҒ“гӮүгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹеӯҗгҒ©гӮӮгҒ®е§ҝгҒҢжө®гҒӢгӮ“гҒ гҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ
гҖҢгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁеҫ…гҒЈгҒҰгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰйҚӢгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁгҖҒз§ҒгҒ®жҸЎгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹйәҰгҒ”гҒҜгӮ“гӮ’дёҖзІ’ж®ӢгҒ•гҒҡйҚӢгҒ«з§»гҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҠж«ғгҒ®дёӯгҒ®йәҰгҒ”гҒҜгӮ“гӮ’еҠ гҒҲгҖҒеЎ©гӮ’е…ҘгӮҢгҒҰгҒҠгҒӢгӮҶгӮ’дҪңгҒЈгҒҹгҖӮеңҹй–“гҒ«гҒӮгҒЈгҒҹйҮҺиҸңгӮ’еҲ»гҒҝе‘іеҷҢжұҒгӮӮдҪңгҒЈгҒҹгҖӮз©әи…№гӮ’жәҖгҒҹгҒҷгҒ«гҒҜи¶ігӮҠгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮд№…гҒ—гҒ¶гӮҠгҒ®гҒҠгҒ„гҒ—гҒ„гҒ”гҒҜгӮ“гҒЁгҒҝгҒқжұҒгҒ«жәҖи¶іж„ҹгӮ’е‘ігӮҸгҒЈгҒҹгҖӮ
дәҢдәәгҒ§гҒҠгҒӢгӮҶгҒЁгҒҝгҒқжұҒгӮ’йЈҹгҒ№гҒҰдёҖж®өиҗҪгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒжҜҚгҒҢзұіж«ғгӮ’й–ӢгҒ‘гҒҹгҖӮиҰ—гҒ„гҒҰгҒ„гҒҹз§ҒгҒҜгҖҢгҒӮгҒЈгҖҒгҒҠзұігҒ гҖҚгҒЁеҸ«гӮ“гҒ гҖӮгҖҢжҜҚгҒЎгӮғгӮ“гҖӮгҒҠзұігҒ гҖҒгҒҠзұігҒҢгҒӮгӮӢгӮҲгҖҚгҒЁиЁҖгҒ„гҒӘгҒҢгӮүйғЁеұӢгҒ®дёӯгӮ’йЈӣгҒігҒҜгҒӯгҒҹгҖӮз§ҒгҒ®е®¶гҒ«гӮӮгҖҒзұіж«ғгҒҜгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒӢгҒӘгӮҠеүҚгҒӢгӮүдёӯгҒ«гҒҜдҪ•гӮӮе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮйәҰгҒ”гҒҜгӮ“гӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гҒҰжүӢгҒ§жҸЎгҒЈгҒҹжҷӮгҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒзұіж«ғгҒ®дёӯгҒёжүӢгӮ’зӘҒгҒЈиҫјгҒҝгҒІгҒЁжҺҙгҒҝгҒ—гҒҰгҖҒеҢӮгҒ„гӮ’гҒӢгҒ„гҒ гҖӮд№…гҒ—гҒ¶гӮҠгҒ®гҒҠзұігҒ®йҰҷгӮҠгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
зұігӮ’жҸЎгӮҠгҒ—гӮҒгҒҹгҒҫгҒҫгҖҒгҒ„гҒӨгҒ—гҒӢз§ҒгҒҜзң гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮжҜҚиҰӘгҒ®гҒҷгҒҷгӮҠжіЈгҒҸеЈ°гҒҢиҒһгҒ“гҒҲгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒ—гҒҹгҖӮжҜҚгҒ«еҪ“жҷӮгҒ®жҖқгҒ„еҮәгӮ’иӘһгҒЈгҒҹжҷӮгҖҒгҖҢжҸЎгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҠзұігҒҢгҒ“гҒјгӮҢиҗҪгҒЎгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҖҒдёЎжүӢгҒ§гӮўгғғеҗӣгҒ®жүӢгӮ’еҢ…гӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгӮүгҖҒгҒӘгӮ“гҒЁгӮӮеҲҮгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҖҒжіЈгҒ„гҒҹгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гӮҸгҒӯгҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҢгӮўгғғеҗӣгҖҒгӮўгғғеҗӣгҖҒгҒ”гҒҜгӮ“гҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгӮҲгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҜҚгҒ®еЈ°гҒ§зӣ®гҒҢиҰҡгӮҒгҒҹгҖӮгҒЎгӮғгҒ¶еҸ°гҒ®дёҠгҒ«гҒҜзҷҪгҒ„ж№Ҝж°—гӮ’з«ӢгҒҰгҒҹгғӣгӮ«гғӣгӮ«гҒ®гҒ”йЈҜгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮз°ЎеҚҳгҒӘгҒҠгҒӢгҒҡгӮӮдҪңгҒЈгҒҰгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒҠгҒӢгҒҡгҒ«гҒҜзӣ®гӮӮгҒҸгӮҢгҒҡгҖҒгҒІгҒҹгҒҷгӮүгҒ”йЈҜгӮ’гҒӢгҒҚгҒ“гӮ“гҒ гҖӮгҖҢгҒҠгҒӢгӮҸгӮҠгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰиҢ¶зў—гӮ’е·®гҒ—еҮәгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жҷӮгҖҒжҜҚгҒ®гҒҶгӮҢгҒ—гҒқгҒҶгҒӘйЎ”гӮ’д№…гҒ—гҒ¶гӮҠгҒ«иҰӢгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жҷӮжҜҚгҒҜеҲҘгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгҒ“гҒ“ж•°гҒӢжңҲгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҖҒжәҖи¶ігҒӘйЈҹдәӢгӮӮгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒгҒ“гҒ®еӯҗгҒҜж „йӨҠеӨұиӘҝгҒ§гҒ„гҒӨдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгӮӮгҒҠгҒӢгҒ—гҒҸгҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ„гҒҚгҒӘгӮҠжәҖи…№гҒ«гҒӘгӮӢгҒҫгҒ§йЈҹгҒ№гҒҹгҒӘгӮүгҖҒгҒӢгҒҲгҒЈгҒҰиә«дҪ“гӮ’еЈҠгҒҷгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮдёӢжүӢгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒжӯ»гҒ¬гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгҒқгҒ®дёҖж–№гҖҒгҒӮгҒ®гҒҫгҒҫжқұдә¬гҒ«гҒ„гҒҹгӮүйЈўйӨ“зҠ¶ж…ӢгҒ§жӯ»гӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮеҗҢгҒҳжӯ»гҒ¬гҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°йЈўйӨ“гҒ§жӯ»гҒ¬гӮҲгӮҠгҒҜгҒҠи…№гҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒ«гҒӘгӮӢгҒҫгҒ§йЈҹгҒ№гҖҒжәҖи¶ігҒ—гҒҰжӯ»гҒӘгҒӣгҒҰгҒӮгҒ’гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
гҒ“гҒ®жҷӮд»ЈгҖҒдёҖз•ӘгҒ®е№ёгҒӣгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒгҒҠи…№гҒҢгҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒ«гҒӘгӮӢгҒҫгҒ§йЈҹгҒ№гӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжҜҚеӯҗж°ҙе…ҘгӮүгҒҡгҒ®е№ёгҒӣгҒӘгҒІгҒЁжҷӮгӮ’жҘҪгҒ—гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒёзҘ–жҜҚгҒҢеё°гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ
иӘ°гӮӮгҒ„гҒӘгҒ„гҒҜгҒҡгҒ®е®¶гҒ®дёӯгҒ«гҒ„гҒҹжқҘе®ўгҒ«гҖҒзҘ–жҜҚгҒҜй©ҡгҒ„гҒҹж§ҳеӯҗгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҖҢгҒҠгҒҶгҖҒгҒҠгҒҶжқҘгҒҹгҒӢгҖҒжқҘгҒҹгҒӢгҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰзӣёеҘҪгӮ’еҙ©гҒ—гҖҒиҫІдҪңжҘӯгҒ§жұҡгӮҢгҒҹгҒҫгҒҫгҒ®жңҚгҒ§з§ҒгӮ’жҠұгҒҚгҒ—гӮҒгҒҹгҖӮ
жҜҚгҒҜгҒ“гҒ“гҒёжқҘгҒҹзҗҶз”ұгӮ’иҝ°гҒ№гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҖҒж–ӯгӮҸгӮҠгӮӮгҒӘгҒҸгҒ”йЈҜгӮ’зӮҠгҒ„гҒҰеӯҗгҒ©гӮӮгҒ«йЈҹгҒ№гҒ•гҒӣгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’и©«гҒігҒҹгҖӮ
гҖҢгҒқгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁи¬қгӮүгӮ“гҒ§гӮӮгҒҲгҒҲгҖӮжқұдә¬гҒ§гҒҜгӮҚгҒҸгҒ«йЈҹгҒ№гӮӢгӮӮгҒ®гӮӮжүӢгҒ«е…ҘгӮүгҒҡгҖҒеӨ§еӨүгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜз”°иҲҺгҒ«жҡ®гӮүгҒ—гҒҰгҒҠгҒЈгҒҰгӮӮзҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮўгғғеҗӣгҒҜгҒҹгӮүгҒөгҒҸйЈҹгҒЈгҒҹгҒӢгҖӮи¶ігӮүгӮ“гҒӢгҒЈгҒҹгӮүгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁзұігӮ’зӮҠгҒ„гҒҰйЈҹгҒ№гҒ•гҒӣгҒҰгӮ„гӮҢгҖҚгҒЁж¶ҷеЈ°гҒ§иӘһгҒЈгҒҹгҖӮ
ж—ҘгҒҢиҘҝгҒ«еӮҫгҒҚгҖҒеҲқеӨҸгҒ®й•·гҒ„дёҖж—ҘгҒҢгӮҲгҒҶгӮ„гҒҸжҡ®гӮҢгҒӢгҒӢгӮӢгҒ“гӮҚгҖҒгғӘгғӨгӮ«гғјгҒ«еҸҺз©«гҒ—гҒҹгҒ°гҒӢгӮҠгҒ®йҮҺиҸңгӮ’д№—гҒӣгҒҹзҘ–зҲ¶гҒҢеё°гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮеӢўгҒ„гӮҲгҒҸе…ҘеҸЈгҒ®жҲёгӮ’й–ӢгҒ‘гҒҰзҘ–зҲ¶гҒҢйЈӣгҒіиҫјгӮ“гҒ§гҒҚгҒҹгҖӮгҖҢгӮ„гҒЈгҒұгӮҠгҒҠеүҚгҒҹгҒЎгҒӢгҖӮ家гҒ®еүҚгҒҫгҒ§жқҘгҒҹгӮүдёӯгҒӢгӮүдәәеЈ°гҒҢиҒһгҒ“гҒҲгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгӮӮеӯҗгҒ©гӮӮгҒ®еЈ°гҒҫгҒ§гҒҷгӮӢгҖӮгҒІгӮҮгҒЈгҒЁгҒ—гҒҰгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгӮ„гҒЈгҒұгӮҠгҒқгҒҶгҒ гҒЈгҒҹгҒӢгҖӮжқұдә¬гҒ§гҒҜгҒҝгӮ“гҒӘз„ЎдәӢгҒӢгҖӮгҒқгҒҶгҒӢгҖҒгҒқгҒҶгҒӢгҖҒгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸз„ЎдәӢгҒ§гӮҲгҒӢгҒЈгҒҹгҖҚгҒЁиЁҖгҒ„гҒӘгҒҢгӮүж¶ҷгӮ’жөҒгҒ—гҒҹгҖӮ
жҲҰдәүгҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҰдёҖе№ҙиҝ‘гҒҸзөҢгҒЁгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®й–“гҖҒжҘҪгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹжҖқгҒ„еҮәгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®ж—ҘгҖҒзҘ–зҲ¶жҜҚгҒЁжҜҚгҒЁејҹгҒ®дә”дәәгҒ§еӣІгӮ“гҒ еӨ•йЈҹгҒҜжң¬еҪ“гҒ«жҘҪгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
жҜҚгҒҜзҘ–зҲ¶жҜҚгҒ«еӯҗдҫӣгӮ’й җгҒ‘гҒҹгӮүгҒҷгҒҗгҒ«жқұдә¬гҒёжҲ»гӮӢгҒӨгӮӮгӮҠгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ гҒҢгҖҒзҘ–зҲ¶жҜҚгҒӢгӮүгҖҒгҒҫгҒ гҒҫгҒ еӨ§еӨүгҒӘжҜҺж—ҘгҒҢз¶ҡгҒҸгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгӮүгҖҒе°‘гҒ—гӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒ—гҒҰж „йӨҠгӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰгҒӢгӮүеё°гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иЁҖгӮҸгӮҢгҖҒдәҢжҷ©гҒ»гҒ©жҺӣеЎҡгҒ®е®¶гҒ«ж»һеңЁгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒз§ҒгӮ’дёҖдәәзҪ®гҒ„гҒҰгҒ„гҒҸдёҚе®үгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ гҖӮ
жөңжқҫй§…гҒҫгҒ§ејҹгӮ’гҒҠгӮ“гҒ¶гҒ—гҒҹжҜҚгӮ’йҖҒгӮҠгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮеҫ…еҗҲе®ӨгҒ®гғҷгғігғҒгҒ«и…°жҺӣгҒ‘гҒҹжҜҚгҒ®йЎ”гҒҢгҒ©гҒ“гҒӢеҜӮгҒ—гҒқгҒҶгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеӯҗгҒ©гӮӮгҒЁеҲҘгӮҢгҒҰжҡ®гӮүгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«еҫҢгӮҚй«ӘгӮ’еј•гҒӢгӮҢгӮӢжҖқгҒ„гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒқгҒ®ж—ҘгҒӢгӮүзҘ–зҲ¶жҜҚгҒЁгҒ®дёүдәәгҒ§гҒ®з”ҹжҙ»гҒҢе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ
гғ»гғ»гғ»гғ»гғ»пјңгӮ«гғ©гӮ№гҒ®иҙҲгӮҠзү©гғ»гҒҠгӮ„гҒӨгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹйӣ‘иҚүгӮ„жҳҶиҷ«пјһгҒёгҒӨгҒҘгҒҸ
гҖҢжҳӯе’ҢеҚҒдёғе№ҙз”ҹгҒҫгӮҢгҒҢгҒ„гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒӘгӮүвҖҰвҖҰгҖҚпјңгҒҠгҒҝеҗӣгҒ®гҒҠгҒЈгҒұгҒ„гғ»еҸ°жүҖгҒ§еҖ’гӮҢгҒ“гӮ“гҒ§гҒ„гҒҹз§ҒпјһзҰҸдә• з« и‘—
 гҒҠгҒҝеҗӣгҒ®гҒҠгҒЈгҒұгҒ„
гҒҠгҒҝеҗӣгҒ®гҒҠгҒЈгҒұгҒ„
жҳӯе’ҢдәҢеҚҒе№ҙе…«жңҲе…ӯж—ҘгҒ«еәғеі¶гҖҒд№қж—ҘгҒ«гҒҜй•·еҙҺгҒ«еҺҹеӯҗзҲҶејҫгҒҢжҠ•дёӢгҒ•гӮҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒҜеҚҒдә”ж—ҘгҒ«з„ЎжқЎд»¶йҷҚдјҸгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҹгҖӮжҳӯе’Ңе…ӯе№ҙпјҲдёҖд№қдёүдёҖпјүгҒ®жәҖе·һдәӢеӨүгҒӢгӮүз¶ҡгҒ„гҒҹеҚҒдә”е№ҙгҒ«еҸҠгҒ¶жҲҰдәүгҒҢгӮҲгҒҶгӮ„гҒҸзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгҖӮи»ҚйғЁгҒ®дёҖйғЁгҒ«гҒҜжңҖеҫҢгҒ®жңҖеҫҢгҒҫгҒ§жҲҰгҒҶгҒЁеҸ«гӮ“гҒ§гҒ„гҒҹиҖ…гӮӮгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ гҒҢгҖҒеӣҪж°‘гҒ®еӨҡгҒҸгҒҜе№іе’ҢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’е–ңгӮ“гҒ гҖӮжҜҚгӮӮгҖҢгҒӮгҒӮгҖҒгӮ„гҒЈгҒЁжҲҰдәүгҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖҚгҒЁе®үе өгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
гҒ гҒҢгҖҒжҲҰдәүгҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮзӣёеӨүгӮҸгӮүгҒҡеӣҪж°‘з”ҹжҙ»гҒҜзӘ®д№ҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮжҲҰдәүгҒҢе§ӢгҒҫгӮӢгҒ“гӮҚгҒӢгӮүз”ҹжҙ»зү©иіҮгҒ®дёҚи¶ігӮ’иЈңгҒҶгҒҹгӮҒгҒ«еҲҮз¬Ұй…ҚзөҰеҲ¶гҒҢгҒЁгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒзү©дёҚи¶ігҒҜгҒҫгҒҷгҒҫгҒҷй…·гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮзү№гҒ«дё»йЈҹгҒ®зұігҒҜгҖҒж•—жҲҰй–“йҡӣгҒ«гҒҜеӨ§дәәдёҖдәәдёҖж—ҘеҪ“гҒҹгӮҠзҙ„дёүзҷҫгӮ°гғ©гғ гҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒҜзҙ„дәҢзҷҫгӮ°гғ©гғ гҒ®й…ҚзөҰгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгӮӮдәҢгҒӢжңҲгӮ„дёүгҒӢжңҲгҒ®йҒ…й…ҚгҒҜеҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰз”ҹжҙ»гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒӢдёҚжҖқиӯ°гҒ«жҖқгҒ„гҖҒеҪ“жҷӮгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жҜҚгҒ«иЁҠгҒӯгҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ
гҖҢжәҖи¶ігҒ«йЈҹгҒ№гӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҒӘгҒҸгҖҒжҜҺж—ҘгҒІгӮӮгҒҳгҒ„жҖқгҒ„гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁжҖқгҒҶгҒ‘гҒ©гҖҒгҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰз”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҒӯгҖҒжҖқгҒ„еҮәгҒӣгҒӘгҒ„гҒӯгҖҚгҒЁжӮІгҒ—гҒқгҒҶгҒӘиЎЁжғ…гӮ’жө®гҒӢгҒ№гҖҒгҒӨгҒ¶гӮ„гҒҸгӮҲгҒҶгҒ«зӯ”гҒҲгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹйЎ”гҒҢгҒ„гҒҫгӮӮеҝҳгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮ
ж•—жҲҰгҒ®зҙ„дёҖе№ҙеүҚгҒ®жҳӯе’ҢеҚҒд№қе№ҙгҒ«ејҹгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮз§ҒгҒҜеӣӣжӯігҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеҚҒеҲҶгҒӘйЈҹгҒ№зү©гҒҢгҒӘгҒҸгҖҒеӨ§дәәгҒ§гӮӮз”ҹгҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§зІҫгҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒ®жҷӮгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒҜгӮӮгҒЈгҒЁеҺігҒ—гҒ„зҠ¶жіҒгҒ®дёӯгҒ«гҒ„гҒҹгҖӮз©әиҘІгҒ®жҒҗжҖ–гҒӢгӮүи§Јж”ҫгҒ•гӮҢгҒҹд№қжңҲгҒ®гҒӮгӮӢж—ҘгҖҒгҒқгҒ®ж—ҘгҒҜгҒҫгҒ гҒҫгҒ еӨҸгҒ®жҡ‘гҒ•гҒҢж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
дёҖжӯігҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ°гҒӢгӮҠгҒ®ејҹгҒҢжҜҚгҒ®д№ігӮ’йЈІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҖӮз§ҒгҒҜејҹгӮ’иҰӢгҒӨгӮҒгҖҢгҒҠгҒҝгҒҸгӮ“гҖҒгҒҠгҒ„гҒ—гҒ„пјҹгҖҚгҒЁеЈ°гӮ’жҺӣгҒ‘гҒҹгҖӮз§ҒгҒҢзҷәгҒ—гҒҹиЁҖи‘үгӮ’иҒһгҒ„гҒҹжҜҚгҒҜгҖҢгӮўгғғеҗӣгӮӮгҒ“гҒ“гҒ«жқҘгҒҰгҒҠгҒҝеҗӣгҒЁдёҖз·’гҒ«гҒҠйЈІгҒҝгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰжүӢжӢӣгҒҚгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ гҒҢз§ҒгҒҜгҖҢгғҖгғЎпјҒгҖҖгҒҠгҒЈгҒұгҒ„гҒҜгҒҠгҒҝгҒҸгӮ“гҒ®гҖҚгҒЁеј·гҒҸжӢ’еҗҰгҒ—гҖҒеә§гҒЈгҒҹгҒҫгҒҫеҫҢгҒҡгҒ•гӮҠгҒ—гҒҹгҖӮ
жҳӯе’ҢдәҢеҚҒе№ҙгҒ®жқұдә¬еӨ§з©әиҘІгҒҜеҫ“жқҘгҒ®и»ҚдәӢж–ҪиЁӯгӮ’зӢҷгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҖҒдәәеҸЈгҒ®еҜҶйӣҶгҒ—гҒҹдёӢз”әгҒӘгҒ©гӮ’дёӯеҝғгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҖҒж°‘й–“дәәгҒҢеӨ§йҮҸгҒ«з„јжӯ»гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹз©әиҘІгҒ®зөҗжһңгҖҒжөҒйҖҡгӮӮеӨ§гҒҚгҒӘиў«е®ігӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒйЈҹзі§дәӢжғ…гҒҜгҒ•гӮүгҒ«жӮӘеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮйЈҹгҒ№зү©гҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©жүӢгҒ«е…ҘгӮүгҒӘгҒ„зҠ¶жіҒгҒ®дёӯгҖҒд№іе‘‘е…җгӮ’жҠұгҒҲгӮӢжҜҚиҰӘгҒ®ж „йӨҠгӮӮжӮӘгҒҸгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒ«еҚҒеҲҶгҒӘд№ігӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒҹгҒЎгҒ®дҪ“еҠӣгҒҜж—ҘгҒ«ж—ҘгҒ«иЎ°гҒҲгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮејҹгҒ®гҒҠгҒҝгҒҸгӮ“гҒ®дҪ“еҠӣгӮӮгҒӢгҒӘгӮҠиҗҪгҒЎгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮд№ійӣўгӮҢгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҖҒз§ҒгҒ®дҪ“еҠӣгӮӮгҒӢгҒӘгӮҠиЎ°гҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ
жҜҚгҒҜгҒқгӮ“гҒӘжҲ‘гҒҢеӯҗгҒ®дҪ“еҠӣгҒҢиҗҪгҒЎгҒҰгҒ„гҒҸгҒ®гҒҢгҒӨгӮүгҒҸгҖҒејҹгӮ’еҜқгҒӢгҒ—гҒӨгҒ‘гӮӢгҒЁж¶ҷгӮ’гҒјгӮҚгҒјгӮҚжөҒгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒҺгӮ…гҒЈгҒЁжҠұгҒҚгҒ—гӮҒгҖҢгҒҠгҒҝеҗӣгҒҜдёҖжқҜйЈІгӮ“гҒ гҒӢгӮүгҖҒд»ҠеәҰгҒҜгӮўгғғеҗӣгҒҢйЈІгҒҝгҒӘгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰиғёгӮ’з§ҒгҒ®йЎ”гҒ«жҠјгҒ—еҪ“гҒҰгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ
гҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҖҢгғҖгғЎгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҒҠгҒҝгҒҸгӮ“гҒ®гҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҖҒдёЎжүӢгҒ§еј·гҒҸжҜҚгҒ®иғёгӮ’жҠјгҒ—гҒ®гҒ‘гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжҜҚгҒҜгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҖҢгҒҠйЎҳгҒ„гҒ гҒӢгӮүйЈІгӮ“гҒ§гҖҚгҒЁз„ЎзҗҶзҹўзҗҶгҒ«гҒ§гӮӮйЈІгҒҫгҒӣгӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒз§ҒгҒҜйғЁеұӢгҒӢгӮүйҖғгҒ’еҮәгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒ е№јгҒӢгҒЈгҒҹгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒйЈІгӮҒгҒ°ејҹгҒ®гҒҠгҒҝеҗӣгҒ®еҲҶгҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶж°—жҢҒгҒЎгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ гҖӮ
еҸ°жүҖгҒ§еҖ’гӮҢгҒ“гӮ“гҒ§гҒ„гҒҹз§Ғ
жҲҰдәүгҒҢзөӮгӮҸгӮҠгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«и»ҚгҒҢж—Ҙжң¬гҒ«йҖІй§җгҒ—гҒҹгҖӮйҖІй§җи»ҚгҒҢдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®е»әзү©гҒҢжҺҘеҸҺгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮе…¬е…ұијёйҖҒгӮӮйҖІй§җи»Қе„Әе…ҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮж•—жҲҰгҒ®зҝҢе№ҙгҒӮгҒҹгӮҠгҒӢгӮүе°‘гҒ—гҒҡгҒӨж”№е–„гҒ•гӮҢгҖҒжқұжө·йҒ“жң¬з·ҡгҒ«жҖҘиЎҢеҲ—и»ҠгҒҢйҒӢиЎҢгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒҹгҒ гҖҒйЈҹзі§дәӢжғ…гҒҜзӣёеӨүгӮҸгӮүгҒҡжӮӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҖҒгӮҖгҒ—гӮҚжӮӘеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
жҳӯе’ҢдәҢеҚҒе№ҙгҒ®жқұдә¬еӨ§з©әиҘІгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжұ иўӢгӮӮдёҖйқўгҒ®з„јгҒ‘йҮҺеҺҹгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеҪ“жҷӮгҖҒз§ҒгҒ®е®ҹ家гҒҜжқҝж©ӢеҢәпјҲзҸҫз·ҙйҰ¬еҢәпјүжұҹеҸӨз”°з”әгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮз©әиҘІгҒ®жҷӮгҖҒз§ҒгӮҲгӮҠеҚҒжӯідёҠгҒ®е…„гҒҜзҮғгҒҲзӣӣгӮӢзҒ«гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒ家гҒ®дёӯгҒ§гӮӮжң¬гҒҢиӘӯгӮҒгӮӢгҒ»гҒ©жҳҺгӮӢгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
жҲҰдәүгҒҢзөӮгӮҸгӮӢгҒЁгҖҒз„јгҒ‘йҮҺеҺҹгҒ®дёӯгҒ«гғӨгғҹеёӮгҒҢзҸҫгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгғӨгғҹеёӮгҒёиЎҢгҒ‘гҒ°еӨ§жҠөгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜжүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒҢеҖӨж®өгҒҜгҒ№гӮүгҒјгҒҶгҒ«й«ҳгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
зұігӮ„йҮҺиҸңгҒӘгҒ©гҖҒжҷ®йҖҡгҒ®еә—гҒёиЎҢгҒЈгҒҰгӮӮз°ЎеҚҳгҒ«жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ§иҝ‘еңЁгҒ®иҫІе®¶гӮ’иЁӘгҒӯгҒҰгҒҜзӣҙжҺҘдәӨжёүгҒ—гҒӘгҒҢгӮүиІ·гҒ„д»ҳгҒ‘гҒ—гҒҹгҖӮжҷӮгҒ«гҒҜзқҖзү©гҒӘгҒ©гҒЁдәӨжҸӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгӮөгғ„гғһгӮӨгғўгҒҢдёҖеҖӢгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгӮӮиІ·гҒЈгҒҹгҖӮ
йЈҹж–ҷгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжҷӮгҒ«гҒҜгғӘгғҘгғғгӮҜгӮөгғғгӮҜгӮ’иғҢиІ гҒ„гҖҒиҮӘе®…гҒӢгӮүдәҢгҖҮгӮӯгғӯгҖҒдёүгҖҮгӮӯгғӯгӮӮйӣўгӮҢгҒҹе·қи¶ҠгҒҫгҒ§жӯ©гҒ„гҒҰеҮәгҒӢгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеҫҖеҫ©гҒҷгӮҢгҒ°дә”гҖҮпҪһе…ӯгҖҮгӮӯгғӯгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮйЈҹж–ҷгҒҢжүӢгҒ«е…ҘгӮҢгҒ°иғҢдёӯгҒ®гғӘгғҘгғғгӮҜгҒҜйҮҚгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮжңқгҖҒжҡ—гҒ„гҒҶгҒЎгҒ«е®¶гӮ’еҮәгҒҰгҖҒ家гҒ«её°гӮҠгҒӨгҒҸгҒ“гӮҚгҒҜеӨңдёӯгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
жҲҰеҫҢеҮҰзҗҶгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒзҢӣзғҲгҒӘгӮӨгғігғ•гғ¬гҒҢйҖІгҒҝгҖҒжҳӯе’ҢдәҢеҚҒдёҖе№ҙдәҢжңҲгҒ«ж–°еҶҶеҲҮжӣҝгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеҗҢгҒҳдёҖеҶҶгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®дёҖеҶҶгҒЁж–°еҶҶгҒ®дёҖеҶҶгҒ§гҒҜдҫЎеҖӨгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮӢгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒй җйҮ‘е°ҒйҺ–гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҖҒдёҖдё–еёҜеҪ“гҒҹгӮҠгҖҒйҠҖиЎҢгҒӢгӮүдёҖгҒӢжңҲгҒ«еј•гҒҚеҮәгҒ—гҒ®гҒ§гҒҚгӮӢйҮ‘йЎҚгҒҜдә”гҖҮгҖҮеҶҶд»ҘеҶ…гҒ«еҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒдҪҝз”ЁгҒ§гҒҚгӮӢзҸҫйҮ‘гӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
зӘ®д№Ҹз”ҹжҙ»гҒ®дёӯгҒ§еҝ…жӯ»гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰи“„гҒҲгҒҹеӣҪж°‘гҒ®гҒҠйҮ‘гӮ’гҖҒеӣҪгҒҜй җйҮ‘е°ҒйҺ–гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжңҖеҫҢгҒ®дёҖеҶҶгҒҫгҒ§гӮӮеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§зү©гҖ…дәӨжҸӣгҒ§йЈҹж–ҷгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®е№ҙгҒ®е…ӯжңҲгҖҒй…ҚзөҰгҒ®д№ҫгғ‘гғігӮ’еҸ—гҒ‘еҸ–гҒЈгҒҰеё°е®…гҒ—гҒҹжҜҚгҒҢгҖҒеҸ°жүҖгҒ§гҒҶгҒӨдјҸгҒӣгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰеҖ’гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢжҲ‘гҒҢеӯҗгӮ’зҷәиҰӢгҒ—гҒҹгҖӮй©ҡгҒ„гҒҰжүӢгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹиҚ·зү©гӮ’ж”ҫгӮҠжҠ•гҒ’гҒҰеӯҗгҒ©гӮӮгҒ®жЁӘгҒ«еә§гӮҠиҫјгӮ“гҒ§жҠұгҒҚгҒӢгҒӢгҒҲгҖҒгҖҢгӮўгғғеҗӣгҖҒгӮўгғғеҗӣгҖӮиө·гҒҚгҒҰгҖҒиө·гҒҚгҒҰгҖӮгҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгҒ®гҖҒзӣ®гӮ’й–ӢгҒ‘гҒҰгҖҒгҒҠйЎҳгҒ„гҖҚгҒЁеӨ§еЈ°гӮ’еҮәгҒ—гҒҰеҝ…жӯ»гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰе‘јгҒігҒӢгҒ‘гҒҹгҖӮ
жҜҚгҒ®жҖқгҒ„гҒҢеӯҗгҒ©гӮӮгҒ«йҖҡгҒҳгҒҹгҒ®гҒӢгҖҒгҒҶгҒЈгҒҷгӮүгҒЁзӣ®гӮ’й–ӢгҒ‘гҒҹгҖӮгҒ гҒҢгҖҒгҒҷгҒҗгҒ«зӣ®гӮ’й–үгҒҳгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ
е№ёгҒ„гҒ«гӮӮеӨ§дәӢгҒ«иҮігӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҒҜгҒ“гҒ®еӯҗгҒҜжӯ»гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒҶгҖҒдёҖеҲ»гӮӮж—©гҒҸзҘ–зҲ¶жҜҚгҒҢгҒ„гӮӢйқҷеІЎгҒ®жҺӣеЎҡгҒёйҖЈгӮҢгҒҰгҒ„гҒҚгҖҒзҷӮйӨҠгҒ•гҒӣгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁиҖғгҒҲгҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒҜзҘ–жҜҚгҒ®е®ҹ家гҒ§гҖҒз•‘гӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒйЈҹгҒ№гӮӢгӮӮгҒ®гҒ гҒ‘гҒҜгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
еӨңгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒиІ·еҮәгҒ—гҒӢгӮүжҲ»гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹзҲ¶гҒ«дәӢгҒ®йЎҡжң«гӮ’и©ұгҒ—гҖҒз§ҒгҒҢе°ҸеӯҰж ЎгҒёе…ҘеӯҰгҒҷгӮӢгҒҫгҒ§жҺӣеЎҡгҒ§й җгҒӢгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮзҘ–зҲ¶жҜҚгҒ«йҖЈзөЎгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдҪҷиЈ•гҒӘгҒ©гҒӘгҒ„гҖӮзҝҢж—ҘгҖҒжқұдә¬й§…гҒ«еҗ‘гҒӢгҒ„гҖҒзҲ¶гҒҢеҲҮз¬ҰгӮ’дәҢжһҡжүӢй…ҚгҒ—гҖҒдёҖз•ӘеҲ—и»ҠгҒ«жҜҚгҒЁејҹгҒ®дёүдәәгҒ§д№—гӮҠиҫјгӮ“гҒ гҖӮ
гҒ“гҒ®жҷӮгҒ®жҜҚгҒҜгҖҒеӣӣжӯігҒ«гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰй–“гҒҢгҒӘгҒ„е№јгҒ„еӯҗгҒҢиҰӘе…ғгҒӢгӮүйӣўгӮҢгҖҒзҘ–зҲ¶жҜҚгҒЁдёүдәәгҒ§гҒҶгҒҫгҒҸз”ҹжҙ»гҒ«йҰҙжҹ“гӮҒгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҒӘгҒ©гҒЁиҖғгҒҲгӮӢдҪҷиЈ•гҒӘгҒ©гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжҺӣеЎҡгҒёиЎҢгҒ‘гҒ°дҪ•гҒЁгҒӢйЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҒ‘гҒҜгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгҒқгӮҢгҒ»гҒ©йЈҹзі§дәӢжғ…гҒҜйҖјиҝ«гӮҲгҒҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гғ»гғ»гғ»гғ»гғ»пјң家ж—ҸгҒЁеҲҘгӮҢйқҷеІЎгҒёгғ»гҒҠгҒ«гҒҺгӮҠгғ»дҪ•гҒӢжңҲгҒ¶гӮҠгҒӢгҒ®гҒҠзұігҒ®гҒ”йЈҜпјһгҒёгҒӨгҒҘгҒҸ
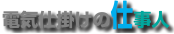
 зҰҸзҘүзі»жғ…е ұиӘҢгҒ®з·ЁйӣҶгҒҜеҫ—ж„ҸеҲҶйҮҺгҒ§гҒҷгҖӮж—ҘеёёжҢҒгҒЎеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҒ„гӮӢжғ…е ұгӮ„гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’з”ҹгҒӢгҒ—гҖҒдјҒз”»гғ»еҸ–жқҗгғ»еҹ·зӯҶгғ»з·ЁйӣҶжүҝгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
зҰҸзҘүзі»жғ…е ұиӘҢгҒ®з·ЁйӣҶгҒҜеҫ—ж„ҸеҲҶйҮҺгҒ§гҒҷгҖӮж—ҘеёёжҢҒгҒЎеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҒ„гӮӢжғ…е ұгӮ„гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’з”ҹгҒӢгҒ—гҖҒдјҒз”»гғ»еҸ–жқҗгғ»еҹ·зӯҶгғ»з·ЁйӣҶжүҝгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
 ж¬ЎгҒё вү«
ж¬ЎгҒё вү«