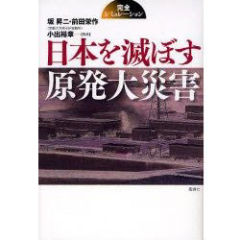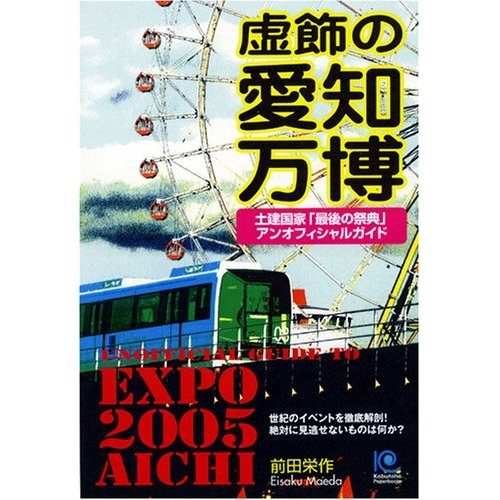гҖҢжҳӯе’ҢеҚҒдёғе№ҙз”ҹгҒҫгӮҢгҒҢгҒ„гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒӘгӮүвҖҰвҖҰгҖҚпјңжҲҰдәүгҒёгҒЁзӘҒгҒҚйҖІгӮҖж—Ҙжң¬гғ»гҒҶгҒ©гӮ“пјһзҰҸдә• з« и‘—
 жҲҰдәүгҒёгҒЁзӘҒгҒҚйҖІгӮҖж—Ҙжң¬
жҲҰдәүгҒёгҒЁзӘҒгҒҚйҖІгӮҖж—Ҙжң¬
з§ҒгҒ®д№іе№је…җжңҹгҒҜжҲҰдәүгҒЁе…ұгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“иЁҳжҶ¶гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒ гҒҢгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®ж—ҘеёёгҒӢгӮүз”ҹжҙ»гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘж§ҳгҖ…гҒӘзү©иіҮгҒҢж¬ЎгҖ…гҒЁе§ҝгӮ’ж¶ҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҖҒгҒ„гҒӢгҒ«д№ҸгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒзҲ¶жҜҚгҒӢгӮүиҒһгҒ„гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ
жҳӯе’ҢеҚҒдә”е№ҙпјҲдёҖд№қеӣӣгҖҮпјүгҒ«гҒҜз Ӯзі–гҖҒгғһгғғгғҒгҒ®еҲҮз¬ҰеҲ¶еәҰгҒҢе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮеҲҮз¬ҰеҲ¶еәҰгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜеҗ„дё–еёҜгҒ®дәәж•°гҒ«еҝңгҒҳгҒҰе“Ғзү©жҜҺгҒ«е№ҙй–“гҒ«иіје…ҘгҒ§гҒҚгӮӢзӮ№ж•°гҒҢжұәгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҖӮз Ӯзі–гӮ„гғһгғғгғҒгӮ’иіје…ҘгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜгҒқгҒ®еҲҮз¬ҰгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒӢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°зӣ®зҡ„гҒЁгҒҷгӮӢе•Ҷе“ҒгҒҜеЈІгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮзӮ№ж•°гӮ’дҪҝгҒ„еҲҮгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®е•Ҷе“ҒгӮ’иіје…ҘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ
жҳӯе’ҢеҚҒе…ӯе№ҙгҖҒгӮігғЎгҒ®й…ҚзөҰеҲ¶еәҰгҒҢе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮй…ҚзөҰеҲ¶гҒҜзұігҒӘгҒ©гҒ®йЈҹж–ҷе“ҒгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒ
ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ«еҝ…иҰҒдёҚеҸҜж¬ гҒ®гӮӮгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹеҲ¶еәҰгҒ§гҖҒжҢҮе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹй…ҚзөҰж—ҘгҒ«й…ҚзөҰжүӢеёігӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҖҒжұәгӮҒгӮүгӮҢгҒҹйҮҸгҒ—гҒӢиіје…ҘгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮеҲҮз¬ҰеҲ¶гӮӮй…ҚзөҰеҲ¶гӮӮгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮзөҢжёҲгӮ’зөұеҲ¶гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«дҪңгӮүгӮҢгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ гҒ‘ж—Ҙжң¬зөҢжёҲгҒҢйҖјиҝ«гҒ—гҖҒж§ҳгҖ…гҒӘзү©иіҮгҒҢзӘ®д№ҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹиЁјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®е№ҙгҒ®еӣӣжңҲгҒ«гҒҜйЈҹе ӮгҒӘгҒ©гҒ§йЈҹеҲёгҒЁеј•гҒҚжӣҝгҒҲгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°йЈІйЈҹгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„еӨ–йЈҹеҲёгҒҢзҷәзөҰгҒ•гӮҢгҒҹгҒҢгҖҒеӨ–йЈҹеҲёгҒ®еҜҫиұЎгҒҜеӨ§дәәгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӯҗдҫӣгҒҜеҜҫиұЎеӨ–гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
жҳӯе’ҢеҚҒе…ӯе№ҙеҚҒдәҢжңҲгҒ®ж—Ҙзұій–ӢжҲҰд»ҘжқҘгҖҒж–°иҒһгҖҒгғ©гӮёгӮӘгҒҜж—Ҙжң¬и»ҚгҒ®йҖЈжҲҰйҖЈеӢқгӮ’дјқгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢй–ӢжҲҰгҒӢгӮүеҚҠе№ҙгӮӮгҒҹгҒҹгҒӘгҒ„жҳӯе’ҢеҚҒдёғе№ҙеӣӣжңҲгҖҒжқұдә¬гҖҒе·қеҙҺгҖҒеҗҚеҸӨеұӢгҖҒеӣӣж—ҘеёӮгҖҒзҘһжҲёгҒӘгҒ©гҒҢгӮўгғЎгғӘгӮ«и»ҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз©әиҘІгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жҷӮгҒҜе®ҹиіӘзҡ„гҒӘиў«е®ігҒҜгҒқгӮҢгҒ»гҒ©гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒз©әиҘІгҒӢгӮүжң¬еңҹгӮ’е®ҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶиЎқж’ғгҒҜеӨ§гҒҚгҒӢгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ гҖӮ
гҒқгҒ®еҫҢгҖҒз©әиҘІгҒҜеҫҗгҖ…гҒ«жҝҖгҒ—гҒ•гӮ’еў—гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҖӮжҳӯе’ҢдәҢеҚҒе№ҙдёүжңҲеҚҒж—ҘгҒ®жқұдә¬еӨ§з©әиҘІгӮ’зҡ®еҲҮгӮҠгҒ«еӨҡгҒҸгҒ®йғҪеёӮгҒҢз©әиҘІгҒ«йҒӯгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгӮӮгҖҒз©әиҘІгҒ®еҜҫиұЎгҒҜи»ҚдәӢж–ҪиЁӯгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒдёҖиҲ¬еә¶ж°‘гҒҢдҪҸгӮҖдҪҸе®…ең°гҒӘгҒ©гӮӮз„Ўе·®еҲҘгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮ
еӣҪж°‘з”ҹжҙ»гҒҢзӘ®д№ҸгҒ—гҖҒжң¬еңҹгҒҢз©әиҘІгҒ«иҰӢиҲһгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒж–°иҒһгҖҒгғ©гӮёгӮӘгҒӘгҒ©гҒҜйҖЈж—ҘгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒж—Ҙжң¬и»ҚгҒҢеҗ„жҲҰең°гҒ§еӢқеҲ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе ұйҒ“гҒ—гҒӢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғһгӮ№гӮігғҹгҒҢеӨ§жң¬е–¶пјҲж—Ҙжң¬и»ҚгҒ®жңҖй«ҳзөұеёҘж©ҹй–ўпјүгҒ®зҷәиЎЁгӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫеһӮгӮҢжөҒгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹзөҗжһңгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҲҰеҫҢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүеӨ§жң¬е–¶зҷәиЎЁгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒиҮӘеҲҶгҒ«йғҪеҗҲгҒ®гҒ„гҒ„еҳҳгӮ’зҷәиЎЁгҒҷгӮӢдҫӢгҒҲгҒ®иЁҖи‘үгҒЁгҒ—гҒҰдҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
з§ҒгҒҢзҸҫеңЁдҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢз”әеҶ…гҒ«гҖҒи»ҚйҡҠзөҢйЁ“гҒ®гҒӮгӮӢд№қеҚҒдёғжӯігҒ®ж–№гҒҢгҒ„гӮүгҒЈгҒ—гӮғгӮӢгҖӮжҲҰдәүдёӯгҒ«зӣ®ж’ғгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢгҒӮгҒҫгӮҠгҒ«гӮӮж®Ӣй…·гҒ§гҖҒи©ұгҒҷгҒ®гӮӮиҫӣгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҚгҖҒгҒЁиЁҖгҒ„гҒӘгҒҢгӮүйҮҚгҒ„еҸЈгӮ’й–ӢгҒ„гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖӮ
гҖҢж–°иҒһиЁҳиҖ…гҒҢеӨ§жң¬е–¶гҒ®зҷәиЎЁгҒЁгҒҜйҒ•гҒҶжң¬еҪ“гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’иЁҳдәӢгҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢгҒҷгҒҗгҒ«зү№й«ҳпјҲзү№еҲҘй«ҳзӯүиӯҰеҜҹпјүгҒ«зҹҘгӮүгӮҢгҖҒйҖ®жҚ•гҒ•гӮҢжӢ·е•ҸгҒ«гҒӢгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еӨ©дә•гҒӢгӮүеҗҠгӮӢгҒ•гӮҢгҖҒдёӯгҒ«гҒҜйҖҶгҒ•еҗҠгӮҠгҒ«гҒ•гӮҢгҒҰжЈ’гҒ§ж®ҙгӮүгӮҢгҖҒеӨұзҘһгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒй ӯгҒӢгӮүж°ҙгӮ’гҒӢгҒ‘гҖҒж„ҸиӯҳгӮ’жҲ»гӮүгҒӣгҒҰгҒҜгҒҫгҒҹжӢ·е•ҸгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’дҪ•еәҰгӮӮдҪ•еәҰгӮӮз№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖҚ
жң¬еҪ“гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жӣёгҒ“гҒҶгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒӘгӮүгҖҒжӢ·е•ҸгҒ«гҒӢгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒӢгҖҒе ҙеҗҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜжӯ»гӮ’иҰҡжӮҹгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮ
жҲҰдәүгҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҰгҒӢгӮүдёғеҚҒж•°е№ҙзөҢгҒЈгҒҹе№іжҲҗдёүеҚҒдёҖе№ҙгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒжҲҰдәүдёӯгҒ«зӣ®ж’ғгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’и©ұгҒ—гҒӘгҒҢгӮүж¶ҷгҒҗгӮ“гҒ§гҒҠгӮүгӮҢгҒҹгҖӮ
еә¶ж°‘гҒ®еӨҡгҒҸгҒҜеӨ§жң¬е–¶зҷәиЎЁгҒ«з–‘е•ҸгӮ’жҢҒгҒӨгӮӮгҒ®гӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮжң¬еҪ“гҒ«жҲҰдәүгҒ§еӢқгҒЎйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ®гҒӘгӮүгҖҒдё–гҒ®дёӯгҒӢгӮүз”ҹжҙ»зү©иіҮгҒҢгҒ©гӮ“гҒ©гӮ“гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒ„гҒҜгҒҡгҒ гҖӮ
жҳӯе’ҢеҚҒе…«е№ҙпјҲдёҖд№қеӣӣдёүпјүгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒжҲ‘гҒҢзҰҸдә•е®¶гҒ§гӮӮи©ұгҒ—еҗҲгҒЈгҒҰзҘ–жҜҚгҒ®е®ҹ家гҒ§гҒӮгӮӢе°Ҹж —е®¶гҒ®гҒӮгӮӢйқҷеІЎзңҢжҺӣеЎҡпјҲзҸҫйқҷеІЎзңҢзЈҗз”°йғЎз«ңжҙӢз”әжҺӣеЎҡпјүгҒёз–Һй–ӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ“гҒ§е°Ҹж —е®¶гҒ®е®¶гҒЁз•‘гӮ’еҖҹгӮҠгҖҒзҘ–зҲ¶жҜҚгҒҢ移гӮҠдҪҸгӮҖгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®жҷӮгҖҒз§ҒгҒҜдёҖжӯіеҚҠгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®е№ҙгҒӢгӮүе°ҸеӯҰж ЎгҒёе…ҘеӯҰгҒҷгӮӢжҳӯе’ҢдәҢеҚҒеӣӣе№ҙпјҲдёҖд№қеӣӣд№қпјүгҒҫгҒ§гҒ®й–“гҖҒж–ӯзүҮзҡ„гҒӘиЁҳжҶ¶гҒӢгӮүиЎқж’ғзҡ„гҒӘд»ҠгӮӮзӣ®гҒ«з„јгҒҚд»ҳгҒ„гҒҰеҝҳгӮҢгӮүгӮҢгҒӘгҒ„иЁҳжҶ¶гҒҫгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҷгҒ№гҒҰгӮ’и©ігҒ—гҒҸиҰҡгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҖҢгҒӮгӮҢгҒҜгҒ„гҒЈгҒҹгҒ„дҪ•гҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиЁҳжҶ¶гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
з§ҒгҒҢй«ҳж Ўз”ҹгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹй ғгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹиЁҳжҶ¶гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжҜҚгҒ«иЁҠгҒӯгҒҹгҖӮеӯҗдҫӣгҒ®гҒ“гӮҚгҒӢгӮүи¬ҺгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰеҝғгҒӢгӮүйӣўгӮҢгҒӘгҒ„гҖҒгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮзҹҘгӮҠгҒҹгҒ„иЁҳжҶ¶гӮӮгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжҜҚгҒӘгӮүз§ҒгҒ®з–‘е•ҸгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзӯ”гҒҲгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒҜгҒҡгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҖҒиЁҳжҶ¶гҒ«ж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹе…үжҷҜгӮ’дёҖгҒӨгҒІгҒЁгҒӨи©ұгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҷгӮӢгҒЁжҜҚгҒҜй©ҡгҒҚгҒ®иЎЁжғ…гҒ§гҖҒжҷӮгҒ«ж¶ҷгӮ’жө®гҒӢгҒ№гҖҒжӮІгҒ—гҒ•гҒЁжӮ”гҒ—гҒ•гҒҢе…ҘгӮҠж··гҒҳгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘйЎ”гҒЁгҒӘгӮҠгҖҢжҲҰдәүгҒҜзө¶еҜҫгҒ«гӮ„гҒЈгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮжҲҰдәүгҒ§иӢҰгҒ—гӮҖгҒ®гҒҜгҒ„гҒӨгӮӮеӣҪж°‘гҒ гҖҚгҒЁиЁҖгҒ„гҒӨгҒӨиӘһгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖӮ
гҒҶгҒ©гӮ“
жҳӯе’ҢеҚҒе…«е№ҙпјҲдёҖд№қеӣӣдёүпјүз§ӢгҖҒгӮҲгҒҶгӮ„гҒҸзүҮиЁҖгӮ’и©ұгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹз§ҒгӮ’иғҢиІ гҒЈгҒҰгҖҒзҘ–жҜҚгҒҢиҝ‘жүҖгҒ®гҒҶгҒ©гӮ“еұӢгҒёгҒҠжҳјгӮ’йЈҹгҒ№гҒ«еҮәгҒӢгҒ‘гҒҹгҖӮеә—гҒ®еӨ–гҒ«гҒҜй•·гҒ„иЎҢеҲ—гҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮзҸҫеңЁгҒ§гҒҜиЎҢеҲ—гҒ®гҒ§гҒҚгӮӢеә—гҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҒҠгҒ„гҒ—гҒ„гҒЁи©•еҲӨгҒ®еә—гҒ гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—жҲҰжҷӮдёӯгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйЈҹгҒ№гӮӢгӮӮгҒ®гҒ«гӮӮдәӢж¬ гҒҸгӮҲгҒҶгҒӘжҜҺж—ҘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮз”әдёӯгҒ®йЈҹе ӮгҒҜгҖҒйЈўгҒҲгҒҹдәәгҒҹгҒЎгҒ§гҒ„гҒӨгӮӮиЎҢеҲ—гҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
еә—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒеёӯгҒҢз©әгҒҸгҒ®гӮ’з«ӢгҒЈгҒҹгҒҫгҒҫеҫ…гҒҹгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ®й–“гҒ«йЈҹеҲёпјҲеӨ–йЈҹеҲёпјүгӮ’еә—гҒ®дәәгҒ«жёЎгҒҷгҖӮгҒҶгҒ©гӮ“гӮ’жүӢжёЎгҒ•гӮҢгҒҹе®ўгҒҜз©әгҒ„гҒҹеёӯгҒ«еә§гӮҠгҖҒй»ҷгҖ…гҒЁгҒҶгҒ©гӮ“гӮ’гҒҷгҒҷгӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҒҶгҒ©гӮ“гҒ®жұҒгӮӮжңҖеҫҢгҒ®дёҖж»ҙгҒҫгҒ§йЈІгҒҝе№ІгҒҷгҖӮйЈҹгҒ№зөӮгҒҲгҒҹе®ўгҒҜгҒҷгҒҗгҒ«еёӯгӮ’з«ӢгҒӨгҖӮгғҶгғјгғ–гғ«гӮ’жӢӯгҒҸй–“гӮӮгҒӘгҒҸж¬ЎгҒ®е®ўгҒҢгҒҶгҒ©гӮ“гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰеә§гӮӢгҖӮгҒқгҒ®з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гӮ„гҒЈгҒЁеә—гҒ«е…ҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒ§гҒҚгҒҹзҘ–жҜҚгҒҢеӨ–йЈҹеҲёгӮ’еә—гҒ®дәәгҒ«жёЎгҒ—гҖҒз§ҒгҒ®еҲҶгӮӮеҗ«гӮҒгҒҶгҒ©гӮ“гӮ’дәҢжқҜжіЁж–ҮгҒ—гҒҹгҖӮгҒҷгӮӢгҒЁеә—гҒ®дәәгҒҜеј·гҒ„еҸЈиӘҝгҒ§гҖҢеӯҗдҫӣгҒ®йЈҹеҲёгҒҜзҷәзөҰгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеӨ§дәәгҒ®йЈҹеҲёгҒ гҒӢгӮүеӯҗгҒ©гӮӮгҒ«гҒҜеҮәгҒӣгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁжӢ’еҗҰгӮ’гҒ—гҒҹгҖӮеӯҗгҒ©гӮӮз”ЁгҒ®йЈҹеҲёгҒҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“зҘ–жҜҚгӮӮжүҝзҹҘгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒз§ҒгҒ®еҲҶгҒЁгҒ—гҒҰжёЎгҒқгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹйЈҹеҲёгҒҜз§ҒгҒ®жҜҚгҒ®йЈҹеҲёгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҢеӯҗгҒ©гӮӮз”ЁгҒ®йЈҹеҲёгҒҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜзҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒ®еӯҗгҒ®жҜҚиҰӘгҒ®йЈҹеҲёгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒҠйЎҳгҒ„гҒ гҒӢгӮүгҖҒгҒ“гҒ®еӯҗгҒ«гӮӮйЈҹгҒ№гҒ•гҒӣгҒҰгӮ„гҒЈгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖҚгҒЁгҖҒжӢқгӮҖгӮҲгҒҶгҒ«й јгҒҝиҫјгӮ“гҒ гҒҢгҖҒеә—гҒ®дәәгҒҜгҖҢгғҖгғЎгҒ гҖҒгғҖгғЎгҒӘгӮӮгҒ®гҒҜгғҖгғЎгҒ гҖҚгҒ®дёҖзӮ№ејөгӮҠгҖӮгҒқгҒ®жҷӮгҖҒз§ҒгҒҜзүҮиЁҖгҒ§гҖҢгӮўгғғгӮҜгғігҒ«гӮӮгҒЎгӮҮгҒҶгҒ гҒ„гҖҒгӮўгғғгӮҜгғігҒ«гӮӮгҒЎгӮҮгҒҶгҒ гҒ„гҖҚгҒЁиЁҖгҒ„гҒӘгҒҢгӮүе·ҰгҒ®жүӢгҒ®е№ігҒ®дёҠгҒ«еҸіжүӢгҒ®з”ІгӮ’д№—гҒӣгҖҒзҘ–жҜҚгҒ®иғҢдёӯгҒӢгӮүиә«гӮ’д№—гӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҒҠйЎҳгҒ„гҒҷгӮӢд»•иҚүгӮ’гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
еә—гҒ®дәәгҒҜиғҢдёӯгҒ®з§ҒгӮ’дёҖзһҘгҒ—гҒҹгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒгҖҢжұәгҒҫгӮҠгҒ гҒӢгӮүеӯҗдҫӣгҒ«гҒҜеҮәгҒӣгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁеҶ·гҒҹгҒҸиЁҖгҒ„ж”ҫгҒЎгҖҒгҖҢйЈҹгҒ№гӮӢгҒ®гҒӢйЈҹгҒ№гҒӘгҒ„гҒ®гҒӢж—©гҒҸжұәгӮҒгҒҰгҒҸгӮҢгҖҚгҒЁзҘ–жҜҚгӮ’дҝғгҒ—гҒҹгҖӮзҘ–жҜҚгҒҜд»•ж–№гҒӘгҒҸгҒҶгҒ©гӮ“гӮ’дёҖжқҜжіЁж–ҮгҒ—гҖҒз©әгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢеёӯгҒ«зқҖгҒҚгҖҒиғҢдёӯгҒӢгӮүз§ҒгӮ’дёӢгӮҚгҒ—гҖҒжҠұгҒЈгҒ“гҒ—гҒҹгҖӮ
е‘ігҒҜдәҢгҒ®ж¬ЎдёүгҒ®ж¬ЎгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹд»Јзү©гҒ§гҖҒгҒҶгҒ©гӮ“гҒ®и…°гҒӘгҒ©гҒҜе…ЁгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮжұҒгҒ®дёҠгҒ«зҷҪгҒҸзҙ°й•·гҒ„гӮӮгҒ®гҒҢжө®гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж„ҹгҒҳгҒ§гҖҒз®ёгҒ§гҒӨгҒҫгӮҖгҒЁз°ЎеҚҳгҒ«еҲҮгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҒӢгҒҫгҒјгҒ“гӮ„гғҠгғ«гғҲгҖҒгғӣгӮҰгғ¬гғігӮҪгӮҰгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе…·гҒӘгҒ©гҒҜе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҖҒеҸЈгҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ гҒ‘гҒ§е№ёгҒӣгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
зҘ–жҜҚгҒҜгҒ¶гҒӨгҒ¶гҒӨгҒ«еҲҮгӮҢгҒҹгҒҶгҒ©гӮ“гӮ’дҪ•еәҰгӮӮз§ҒгҒ®еҸЈгҒ«йҒӢгӮ“гҒ гҖӮз§ҒгҒҜгҒқгӮҢгӮ’гҒҶгӮҢгҒ—гҒқгҒҶгҒ«йЈҹгҒ№гҒҹгҖӮгҒқгӮ“гҒӘеӯ«гҒ®йЎ”гӮ’иҰӢгҒӘгҒҢгӮүгҖҒд»ҠгҒ®дё–гҒ®дёӯгҒ®зҗҶдёҚе°ҪгҒ•гҖҒиҮӘеҲҶгҒ§гҒҜгҒ©гҒҶгҒ«гӮӮгҒӘгӮүгҒӘгҒ„жӮ”гҒ—гҒ•гҖҒе¬үгҒ—гҒқгҒҶгҒ«гҒҶгҒ©гӮ“гӮ’йЈҹгҒ№гӮӢеӯ«гҒ®е§ҝгҒ®дёҚжҶ«гҒ•гҒӘгҒ©гҒҢе…ҘгӮҠж··гҒҳгӮҠгҖҒжҖқгӮҸгҒҡж¶ҷгҒҗгӮ“гҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
гҖҢгҒҠгҒ°гҒӮгҒЎгӮғгӮ“гҖҒгҒҠи…№дёҖжқҜгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеЈ°гҒ«жҲ‘гҒ«иҝ”гҒЈгҒҹзҘ–жҜҚгҒҜгҖҒеӯ«гҒ®йЈҹгҒ№ж®ӢгҒ—гҒҹгҒҶгҒ©гӮ“гӮ’гҒ•гӮүгҒҲгҖҒжұҒгӮӮе…ЁгҒҰйЈІгҒҝе№ІгҒ—гҖҒеҶҚгҒіз§ҒгӮ’иғҢиІ гҒҶгҒЁгҒқгҒқгҒҸгҒ•гҒЁеә—гӮ’еҮәгҒҹгҖӮгҒҶгҒ©гӮ“еұӢгҒ®еҜҫеҝңгҒ®й…·гҒ•гҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒгҒқгӮ“гҒӘеҜҫеҝңгӮ’гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹзӨҫдјҡгҒҢжӮ”гҒ—гҒҸгҖҒ家гҒ«её°гӮҠгҒӨгҒҸгӮ„еҗҰгӮ„гҖҒгӮҰгғҜгӮЎвҖ•гҒЁжіЈгҒҚеҙ©гӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
ж—Ҙеў—гҒ—гҒ«жӮӘеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸйЈҹзі§дәӢжғ…гӮ„гӮўгғЎгғӘгӮ«и»ҚгҒ«гӮҲгӮӢз©әиҘІгҒ«еӮҷгҒҲгҖҒзҘ–зҲ¶жҜҚгҒҢйқҷеІЎзңҢжҺӣеЎҡпјҲзҸҫйқҷеІЎзңҢзЈҗз”°йғЎз«ңжҙӢз”әжҺӣеЎҡпјүгҒ«з–Һй–ӢгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгҒқгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰеҚҠе№ҙгҒ»гҒ©зөҢгҒЈгҒҹжҳӯе’ҢеҚҒд№қе№ҙеӣӣжңҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гғ»гғ»гғ»гғ»гғ»пјңгҒҠгҒҝеҗӣгҒ®гҒҠгҒЈгҒұгҒ„гғ»еҸ°жүҖгҒ§еҖ’гӮҢгҒ“гӮ“гҒ§гҒ„гҒҹз§ҒпјһгҒёгҒӨгҒҘгҒҸ
гҖҢжҳӯе’ҢеҚҒдёғе№ҙз”ҹгҒҫгӮҢгҒҢгҒ„гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒӘгӮүвҖҰвҖҰгҖҚпјңгҒҫгҒҲгҒҢгҒҚгғ»зҘ–жҜҚгҒ®еҶҚе©ҡпјһгҖҖзҰҸдә• з« и‘—

гҒҫгҒҲгҒҢгҒҚ
жҳӯе’ҢдёүеҚҒе…ӯе№ҙй«ҳж ЎгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҖҒж°ёи°·ең’жң¬иҲ—гҒ«е°ұиҒ·гҒ—гҒҹгҖӮе–¶жҘӯиҒ·гҒЁгҒ—гҒҰе…ЁеӣҪгҒіеӣһгӮҠгҖҒж§ҳгҖ…гҒӘзөҢйЁ“гӮ’гҒ•гҒӣгҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҹгҖӮд»•дәӢгҒҜжҘҪгҒ—гҒҸгҖҒе……е®ҹгҒ—гҒҹж—ҘгҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжҳӯе’ҢеӣӣеҚҒдә”е№ҙгҖҒзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁдёҖеҝөзҷәиө·гҒ—гҒҰйҖҖиҒ·гҒ—гҖҒдәӢжҘӯгӮ’е§ӢгӮҒгҒҹгҖӮгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®дәӢжҘӯгӮ’зөҢйЁ“гҒ—гҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«е…ӯгҖҮеёӯгҒ®е–«иҢ¶еә—зөҢе–¶гҒ«иҗҪгҒЎзқҖгҒ„гҒҹгҖӮзөҗж§Ӣе®ҹе…ҘгӮҠгҒҢгӮҲгҒҸгҖҒеёёйҖЈе®ўгҒЁгӮӮд»ІиүҜгҒҸгҒӘгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒжҘҪгҒ—гҒҸжҜҺж—ҘгӮ’йҒҺгҒ”гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮгҒӮгӮӢж—ҘгҖҒе№ҙй…ҚгҒ®еёёйҖЈе®ўгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹеҗҚеҸӨеұӢеӨ§еӯҰж•ҷжҺҲгҒӢгӮүгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҜдҪ•е№ҙз”ҹгҒҫгӮҢгҒ§гҒҷгҒӢгҒЁиҒһгҒӢгӮҢгҖҒжҳӯе’ҢеҚҒдёғе№ҙгҒ§гҒҷгҒЁзӯ”гҒҲгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҹгҒЎгҒ®дё–д»ЈгӮӮгҒ„гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮгҒқгҒ®жҷӮгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮүгҖҒж—Ҙжң¬гҒҜеҶҚгҒіжҲҰдәүгҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁж„ҸеӨ–гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’иЁҖгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮ
гҒӢгҒӨгҒҰгҖҒжҲҰеүҚжҙҫгҖҒжҲҰдёӯжҙҫгҖҒжҲҰеҫҢжҙҫгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮжҲҰдәүгӮ’зӣҙжҺҘдҪ“йЁ“гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜжҲҰеүҚжҙҫгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгӮӮжҳӯе’ҢдёҖжЎҒз”ҹгҒҫгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®дәәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҲҰдәүгҒ®жӮІжғЁгҒ•гҖҒдёҚжқЎзҗҶгӮ’иӘһгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒҜзӣҙжҺҘжҲҰдәүгҒ®жӮІжғЁгҒ•гӮ’дҪ“йЁ“гҒ—гҒҹжҲҰеүҚжҙҫгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢдәәйҒ”гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
жҲҰдёӯз”ҹгҒҫгӮҢгҒ®з§ҒгҒҹгҒЎгҒ®дё–д»ЈгҒ®дёӯгҒ«гӮӮгҖҒиҰӘгҒ«жҠұгҒҲгӮүгӮҢйҳІз©әеЈ•гҒёйҖғгҒ’иҫјгӮ“гҒ иЁҳжҶ¶гӮ’гҒӢгҒҷгҒӢгҒ«з•ҷгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢдәәгҒҜгҒ„гӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжҳӯе’ҢеҚҒдёғе№ҙз”ҹгҒҫгӮҢгҒ«гӮӮгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒжҝҖгҒ—гҒ„з©әиҘІгҒ®иЁҳжҶ¶гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒҫгҒ иөӨеӯҗгҒ§жҜҚгҒ®иғҢдёӯгҒ«гҒҠгӮ“гҒ¶
гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгӮ“гҒӘжҲҰдёӯжҙҫгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒжҲҰеҫҢгҒ®йЈўгҒҲгӮ’дҪ“йЁ“гҒ—гҒҹиЁҳжҶ¶гҒҜгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒЁеҝғгҒ«еҲ»гҒҝиҫјгҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдәҢеәҰгҒЁгҒӮгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘз”ҹжҙ»гҒ«жҲ»гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮжҲҰдәүдҪ“йЁ“гҒҜе…өйҡҠгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гҒӨгӮүгҒ„зөҢйЁ“гӮ„з©әиҘІгҒӢгӮүйҖғгҒ’еӣһгҒЈгҒҹзөҢйЁ“гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮйЈўгҒҲгҒ®иӢҰгҒ—гҒҝгӮӮгӮҢгҒЈгҒҚгҒЁгҒ—гҒҹжҲҰдәүзөҢйЁ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
жҳӯе’ҢеҚҒдёғе№ҙгҒҫгҒ§гҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгҒҹиҖ…гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹйЈўгҒҲгҒ®иӢҰгҒ—гҒҝгӮ’иә«гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰзөҢйЁ“гҒ—гҖҒиЁҳжҶ¶гҒ«з•ҷгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҢжҳӯе’ҢеҚҒе…«е№ҙз”ҹгҒҫгӮҢгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒйЈўгҒҲгҒ®иӢҰгҒ—гҒҝгҒ®иЁҳжҶ¶гӮӮгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮйЈўгҒҲгҒ§иӢҰгҒ—гӮ“гҒ зөҢйЁ“гӮ’иӘһгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹжҷӮгҖҒеҶҚгҒіжҲҰдәүгҒёгҒ®йҒ“гӮ’жӯ©гҒҝе§ӢгӮҒгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ©гҒҶиҖғгҒҲгҒҰгӮӮжҲҰдәүгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҖҒгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҒҜзҠҜзҪӘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгӮӮеӣҪ家гҒ«гӮҲгӮӢжңҖеӨ§гҒ®зҠҜзҪӘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҲҰдәүгҒҜзӣҙжҺҘзҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒжҲҰеҫҢгҒ®йЈўгҒҲгҒ«иӢҰгҒ—гӮ“гҒ еӯҗгҒ©гӮӮгҒҹгҒЎгҒҜгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ„гӮӢгҖӮжҳӯе’ҢеҚҒдёғе№ҙз”ҹгҒҫгӮҢгҒ®з§ҒгӮӮгҒқгӮ“гҒӘдҪ“йЁ“иҖ…гҒ®дёҖдәәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
В
зҘ–жҜҚгҒ®еҶҚе©ҡ
еӨ§жӯЈдәҢе№ҙпјҲдёҖд№қдёҖдёүпјүеҚҒдёҖжңҲгҖҒжқұдә¬еёӮж·ұе·қеҢәпјҲзҸҫжқұдә¬йғҪжұҹжқұеҢәпјүгҒ§жңқжҜ”еҘҲж–°е№ігҒЁеҰ»вҖңгҒқгҒ®вҖқгҒЁгҒ®й–“гҒ«дәҢдәәзӣ®гҒ®еҘігҒ®еӯҗгҒҢз”ЈеЈ°гӮ’дёҠгҒ’гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҢз§ҒгҒ®жҜҚвҖңеҚғд»ЈвҖқгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҘігҒ®еӯҗгҒҜдёЎиҰӘгҒЁе§үгҒ®вҖңгҒ—гҒ®вҖқгҒ«еҸҜж„ӣгҒҢгӮүгӮҢгҖҒеҒҘгӮ„гҒӢгҒ«иӮІгҒЎгҖҒгӮ„гҒҢгҒҰе°ҸеӯҰж ЎгҒёе…ҘеӯҰгҒ—гҒҹгҖӮ
д№қжӯігҒ«гҒӘгҒЈгҒҹеӨ§жӯЈеҚҒдәҢе№ҙпјҲдёҖд№қдәҢдёүпјүд№қжңҲдёҖж—ҘгҖҒгҒқгҒ®ж—ҘгҒ®жҳҺгҒ‘ж–№гҒ®еӨ©ж°—гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠиүҜгҒҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢеҫҗгҖ…гҒ«еӣһеҫ©гҒ—гҖҒжҳјиҝ‘гҒҸгҒ«гҒҜи’ёгҒ—жҡ‘гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеҘігҒ®еӯҗгҒ®зҲ¶гҒҜгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«д»•дәӢгҒ«еҮәгҒӢгҒ‘гҖҒвҖңеҚғд»ЈвҖқгҒЁвҖңгҒ—гҒ®вҖқгҒҜе°ҸеӯҰж ЎгҒёгҒЁеҮәгҒӢгҒ‘гҒҹгҖӮжҘҪгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹеӨҸдј‘гҒҝгҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҹзҝҢж—ҘгҒ®е§ӢжҘӯејҸгҒ®ж—ҘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮд№…гҒ—гҒ¶гӮҠгҒ«еҸӢйҒ”гҒЁдјҡгҒ„гҖҒеӨҸдј‘гҒҝгҒ®жҖқгҒ„еҮәгӮ’иӘһгӮҠгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжҳјеүҚгҒ«гҒҜвҖңеҚғд»ЈвҖқгҒЁвҖңгҒ—гҒ®вҖқгҒҜеӯҰж ЎгӮ’еҮәгҒҹгҖӮ家гҒ§гҒҜй–“гӮӮгҒӘгҒҸеё°е®…гҒҷгӮӢгғӢдәәгҒ®еӯҗдҫӣгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒвҖңгҒқгҒ®вҖқгҒҢгҒҠжҳјеҫЎйЈҜгҒ®ж”ҜеәҰгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгҒ®ж—ҘгӮӮе№іеҮЎгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒе№ёгҒӣгҒӘж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒҢз№°гӮҠеәғгҒ’гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
зӘҒеҰӮгҖҒгғүгғүгғјгғігҒЁгҒ„гҒҶеӨ§гҒҚгҒӘең°йіҙгӮҠгҒҢгҒ—гҒҹгҒӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҹзһ¬й–“гҖҒең°йқўгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸжҸәгӮүгҒҺгҒ гҒ—гҒҹгҖӮйӣ»жҹұгӮ„家гҖ…гҒҢгҒҗгӮүгҒҗгӮүгҒЁжҸәгӮҢгӮӢгҖӮеЎҖгӮӮжҸәгӮҢгӮӢгҖӮ家гҒ®дёӯгҒ§гҒҜжҲёжЈҡгҒӢгӮүйЈҹеҷЁгҒҢйЈӣгҒіеҮәгҒ—гҒҰз •гҒ‘ж•ЈгӮҠгҖҒжҲёжЈҡгӮ„гӮҝгғігӮ№гҒҢеәҠгҒ®дёҠгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘйҹігҒЁгҒЁгӮӮгҒ«еҖ’гӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ家гҒ®еЈҒпјҲеңҹеЈҒпјүгҒ«гҒҜгҒҝгӮӢгҒҝгӮӢгҒҶгҒЎгҒ«дәҖиЈӮгҒҢе…ҘгӮҠгҖҒеЈҒгҒ®дёӯгҒ«гҒӮгӮӢз«№гҒ§гҒ§гҒҚгҒҹйӘЁзө„гҒҝгҒҢгҒӮгӮүгӮҸгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеұӢж №гҒӢгӮүгҒҜз“ҰгҒҢеүҘгҒҢгӮҢиҗҪгҒЎгҖҒ家гҒҢеҖ’еЈҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮ
ең°йңҮзҷәз”ҹжҷӮгҖҒжҳјйЈҹжҷӮгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮ
гҒЈгҒҰгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®е®¶гҒ§зҒ«гӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
В
еҪ“жҷӮгҖҒиӘҝзҗҶгҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒйўЁе‘ӮгӮ„гҒҠж№ҜгӮ’жІёгҒӢгҒҷгҒҹгӮҒи–ӘгӮ„зӮӯгҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮйҮңжҲёгҒҜеӣәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢз·ҙзӮӯгӮ„зӮӯгӮ’дҪҝгҒҶдёғијӘгҒҜжүӢгҒ§жҢҒгҒЈгҒҰз°ЎеҚҳгҒ«з§»еӢ•гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮдёғијӘгҒ®дёҠгҒ«ијүгҒӣгҒҰгҒӮгӮӢйҚӢгҒҢи»ўгҒ’иҗҪгҒЎгҖҒдёғијӘгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гӮӮжЁӘеҖ’гҒ—гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеҙ©гӮҢгӮӢйҮңжҲёгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒзҒ«гҒҢгӮҖгҒҚеҮәгҒ—гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®зҒ«гҒ®дёҠгҒ«еҖ’гӮҢгҒҹ家財йҒ“е…·гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜеҖ’гӮҢгҒҹжҹұгӮ„еұӢж №гҒҢиҰҶгҒ„гҒӢгҒ¶гҒ•гӮҠзҒ«гҒҢгҒӨгҒ„гҒҹгҖӮз”әгҒ®гҒӮгҒЎгӮүгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮүзҒ«гҒ®жүӢгҒҢдёҠгҒҢгҒЈгҒҹгҖӮ
жӯ»иҖ…гҖҒиЎҢж–№дёҚжҳҺиҖ…еҚҒдёҮдә”гҖҮгҖҮгҖҮдәәд»ҘдёҠгҖҒе…ЁеЈҠ家еұӢзҙ„еҚҒдёҮд№қгҖҮгҖҮгҖҮжЈҹгҖҒз„јеӨұ家еұӢзҙ„дәҢеҚҒдёҖдёҮжЈҹгӮӮгҒ®еӨ§иў«е®ігӮ’еҮәгҒ—гҒҹй–ўжқұеӨ§йңҮзҒҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
дәәгҖ…гҒҜиҝ«гӮҠгҒҸгӮӢзҒ«гӮ’йҒҝгҒ‘йҖғгҒ’жғ‘гҒЈгҒҹгҖӮвҖңеҚғд»ЈвҖқгҒҜе§үгҒ®вҖңгҒ—гҒ®вҖқгӮ’жҺўгҒқгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹгҒҢиҰӢгҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖҒжҖҘгҒ„гҒ§е®¶гҒёеё°гӮҚгҒҶгҒЁиө°гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒдҪ•гҒӢеӨ§еЈ°гҒ§еҸ«гҒігҒӘгҒҢгӮүиҮӘе®…гҒ®гҒӮгӮӢж–№еҗ‘гҒӢгӮүйҖғгҒ’гҒҰгҒҸгӮӢдәәжіўгҒ«жҠјгҒ•гӮҢйҖІгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгӮүгҒ„гҒ„гҒӢгӮҸгҒӢгӮүгҒҡгҒ«гҒ„гӮӢгҒЁгҖҒиҰӢзҹҘгӮүгҒ¬дәәгҒҢгҖҢеҚұгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒ“гҒЈгҒЎгҒёгҖҒж—©гҒҸгҖҒж—©гҒҸгҖҚгҒЁеЈ°гӮ’гҒӢгҒ‘гҖҒжүӢгӮ’еј•гҒ„гҒҰдёҖз·’гҒ«йҖғгҒ’гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖӮжҒҗжҖ–гҒЁе§үгӮ„жҜҚиҰӘгҒЁгӮӮдјҡгҒҲгҒҡгҖҒжіЈгҒҚгҒҳгӮғгҒҸгӮӢгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„е№јгҒ„вҖңеҚғд»ЈвҖқгҒ«гҖҒгҖҢеӨ§дёҲеӨ«гҒ гҒӢгӮүгҒӯгҖҚгҖҢеӨ§дёҲеӨ«гҒ гӮҲгҖҚгҒЁеҠұгҒҫгҒ—гҒ®еЈ°гӮ’гҒӢгҒ‘гҒӘгҒҢгӮүгҖҒе®үе…ЁгҒӘе ҙжүҖгҒёйҒҝйӣЈгҒ•гҒӣгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖӮ
гҒҠжҜҚгҒ•гӮ“гӮ„гҒҠе§үгҒЎгӮғгӮ“гҖҒгҒҠзҲ¶гҒ•гӮ“гҒҜгҒ©гҒ“гҒ«гҒ„гӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒЁеҝғй…ҚгҒЁдёҚе®үгҒ§д»•ж–№гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҖ’еЈҠгҒ—гҒҹ家еұӢгӮ„гҒӮгҒЎгӮүгҒ“гҒЎгӮүгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢзҒ«гҒ®жүӢгҖҒдәәгҖ…гҒ®е–§йЁ’гҒҜжіЈгҒҸгҒ“гҒЁгҒҷгӮүеҝҳгӮҢгҒ•гҒӣгҒҹгҖӮ
еӨ•ж–№иҝ‘гҒҸгҒ«гҒӘгӮҠзҒ«зҒҪгӮӮгӮ„гӮ„дёӢзҒ«гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹй ғгӮ’иҰӢиЁҲгӮүгҒ„гҖҒ家гҒ«жҲ»гҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҫгҒ§иҰӢж…ЈгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹйўЁжҷҜгҒҜдёҖеӨүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮиҮӘеҲҶгҒ®е®¶гҒҜгҒ©гҒҶгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖҒгҒҠе§үгҒЎгӮғгӮ“гҖҒгҒҠжҜҚгҒ•гӮ“гҒҹгҒЎгҒҜз„ЎдәӢгҒӘгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҒЁжҖқгҒ„гҒӘгҒҢгӮү家гҒҫгҒ§гҒҹгҒ©гӮҠзқҖгҒҸгҒЁгҖҒ家гҒҜе®Ңе…ЁгҒ«з„јеӨұгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮе‘ЁгӮҠгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹ家гӮӮгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒҢз„јеӨұгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮе№јгҒ„еӯҗдҫӣгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒ®е…үжҷҜгҒҜгӮ·гғ§гғғгӮҜгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ гҒҢгҖҒе§үгҒ®е§ҝгӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гҒҹгҒ“гҒЁгҒ®е–ңгҒігӮӮеӨ§гҒҚгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮз„јгҒ‘и·ЎгҒ§гҖҒгҒӘгҒҷгҒҷгҒ№гӮӮгҒӘгҒҸдәҢдәәгҒ§дҪҮгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒЁгҖҒжҜҚгҒҢжҲ»гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҒ—гҒ°гӮүгҒҸзөҢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§зҲ¶гҒҢжҲ»гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸ家ж—Ҹе…Ёе“ЎгҒҢз„ЎдәӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’е–ңгҒігҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
з„ЎдәӢгҒ®еҶҚдјҡгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒең°йңҮгҒ®иў«е®ігҒҜз”ҡеӨ§гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮз„јеӨұгҒ—гҒҹ家гҒ®еҶҚе»әгҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒд»•дәӢгҒ®гҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҒ§гҖҒзҲ¶ж–°е№ігҒҜеҝғеҠҙгҒҢгҒҹгҒҫгӮҠгҖҒ次第次第гҒ«иӮүдҪ“гҒҢиқ•гҒҫгӮҢгҖҒйңҮзҒҪгҒӢгӮүзҙ„дёҖе№ҙеҫҢгҖҒгҒӨгҒ„гҒ«её°гӮүгҒ¬дәәгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮвҖңгҒқгҒ®вҖқгҒҜе№јгҒ„дәҢдәәгҒ®еЁҳгӮ’йӨҠгҒҶгҒҹгӮҒгҖҒзёҒж•…гӮ’й јгҒЈгҒҰи—ӨеҖүйӣ»з·ҡгҒ«е°ұиҒ·гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰиҒ·е ҙгҒ®дёҠеҸёгҒ®зҙ№д»ӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒжҳӯе’Ңдә”е№ҙгҖҒзҰҸдә•дҪңе№ігҒЁеҶҚе©ҡгӮ’гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҫгҒ§жңқжҜ”еҘҲгҒ®иӢ—еӯ—гӮ’еҗҚд№—гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢвҖңгҒқгҒ®вҖқгҒ®еҶҚе©ҡгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзҰҸдә•е§“гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжңқжҜ”еҘҲгҒ®еҗҚеүҚгҒҜж®ӢгҒ•гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒе§үвҖңгҒ—гҒ®вҖқгҒ®е§“гҒҜеӨүгҒҲгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮеҗҢгҒҳ家ж—ҸгҒ§гҒӮгӮҠгҒӘгҒҢгӮүзҲ¶жҜҚгҒЁдёӢгҒ®еЁҳвҖңеҚғд»ЈвҖқгҒ®дёүдәәгҒҜзҰҸдә•е§“гҖҒдёҠгҒ®еЁҳвҖңгҒ—гҒ®вҖқгҒҜжңқжҜ”еҘҲ姓гҒ§жҡ®гӮүгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
й–ўжқұеӨ§йңҮзҒҪгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒж—Ҙжң¬зөҢжёҲгҒҜеӨ§гҒҚгҒӘжү“ж’ғгӮ’иў«гҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰйңҮзҒҪжүӢеҪўгҒҢдёҚиүҜеӮөжЁ©еҢ–гҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒ«жҳӯе’ҢдәҢе№ҙпјҲдёҖд№қдәҢдёғпјүгҖҒ
В
еҪ“жҷӮгҒ®зүҮеІЎи”өзӣёгҒ®гҖҢжқұдә¬жёЎиҫәйҠҖиЎҢгҒҢз ҙз”ЈгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁгҒ®еӨұиЁҖгӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘йЁ’гҒҺгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒжҳӯе’ҢгҒ®йҮ‘иһҚжҒҗж…ҢгҒёгҒЁгҒӨгҒӘгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮжҳӯе’Ңеӣӣе№ҙпјҲдёҖд№қдәҢд№қпјүгҒ«гҒҜгӮўгғЎгғӘгӮ«еҗҲиЎҶеӣҪгҒ®гғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜгҒ§гҒ®ж ӘдҫЎжҡҙиҗҪгӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒЁгҒ—гҒҰдё–з•ҢжҒҗж…ҢгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҒқгҒ®жіўгҒ«ж—Ҙжң¬гӮӮйЈІгҒҝиҫјгҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®гҒ“гӮҚгҒӢгӮүгҖҒж—Ҙжң¬гҒҜжҖҘйҖҹгҒ«и»ҚеӣҪдё»зҫ©гҒ®йҒ“гҒёгҒЁзӘҒгҒҚйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҸгҖӮжҳӯе’Ңе…ӯе№ҙпјҲдёҖд№қдёүдёҖпјүгҒ®жәҖе·һдәӢеӨүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒҜжәҖе·һеӣҪгӮ’е»әеӣҪгҒҷгӮӢгҖӮ
вҖңеҚғд»ЈвҖқвҖҷгҒҜе№ҙй ғгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮзҫ©зҲ¶гҒ§гҒӮгӮӢзҰҸдә•дҪңе№ігҒӢгӮүиҰӢеҗҲгҒ„и©ұгӮ’еӢ§гӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒвҖңеҚғд»ЈвҖқгҒҜеүҚеҺҹйҖІдёҖгҒЁгҒ„гҒҶжҒӢдәәгҒҢгҒ„гҒҹгҖӮдҪңе№ігҒҜеүҚеҺҹгҒЁгҒ®зөҗе©ҡгҒ«зҢӣеҸҚеҜҫгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒзөҗеұҖгҒҜвҖңеҚғд»ЈвҖқгҒ®ж„ҸжҖқгӮ’жӣІгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒзҰҸдә•е®¶гҒ«йӨҠеӯҗгҒ«е…ҘгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жқЎд»¶гҒ«дәҢдәәгҒ®зөҗе©ҡгӮ’иЁұгҒ—гҒҹгҖӮ
жҳӯе’ҢеҚҒдәҢе№ҙпјҲдёҖд№қдёүдёғпјүгҒӢгӮүж—ҘдёӯжҲҰдәүгҒҢе§ӢгҒҫгӮҠгҖҒжҳӯе’ҢеҚҒе…ӯе№ҙпјҲдёҖд№қеӣӣдёҖпјүеҚҒдәҢжңҲе…ӯж—ҘгҒӢгӮүгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒЁгҒ®й–“гҒ®еӨӘе№іжҙӢжҲҰдәүгҒёгҒЁзӘҒе…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮ
еӨӘе№іжҙӢжҲҰдәүгҒҢе§ӢгҒҫгӮӢеүҚгҖҒз§ҒгҒ®дёҖ家гҒҜгҒҫгҒ жӯҰи”өйҮҺгҒ®йқўеҪұгҒҢиүІжҝғгҒҸж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹжқҝж©ӢеҢәпјҲзҸҫз·ҙйҰ¬еҢәпјүгҒ«еұ…гӮ’ж§ӢгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒзҲ¶гҒҢеҗҚеҸӨеұӢеёӮгҒёи»ўеӢӨгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒз§ҒгҒҜжҳӯе’ҢеҚҒдёғе№ҙпјҲдёҖд№қеӣӣдәҢпјүеӣӣжңҲдәҢж—ҘгҒ«еҗҚеҸӨеұӢеёӮжҳӯе’ҢеҢәгҒ§е‘ұе‘ұгҒ®еЈ°гӮ’дёҠгҒ’гҒҹгҖӮгҒ гҒҢгҖҒдёҖе№ҙгӮӮзөҢгҒҹгҒ¬жҳӯе’ҢеҚҒе…«е№ҙжҳҘгҖҒеҶҚгҒіе®¶ж—ҸгҒқгӮҚгҒЈгҒҰжқҝж©ӢеҢәгҒёжҲ»гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
гғ»гғ»гғ»гғ»гғ»пјңжҲҰдәүгҒёгҒЁзӘҒгҒҚйҖІгӮҖж—Ҙжң¬гғ»гҒҶгҒ©гӮ“пјһгҒёгҒӨгҒҘгҒҸ
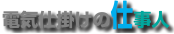
 зҰҸзҘүзі»жғ…е ұиӘҢгҒ®з·ЁйӣҶгҒҜеҫ—ж„ҸеҲҶйҮҺгҒ§гҒҷгҖӮж—ҘеёёжҢҒгҒЎеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҒ„гӮӢжғ…е ұгӮ„гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’з”ҹгҒӢгҒ—гҖҒдјҒз”»гғ»еҸ–жқҗгғ»еҹ·зӯҶгғ»з·ЁйӣҶжүҝгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
зҰҸзҘүзі»жғ…е ұиӘҢгҒ®з·ЁйӣҶгҒҜеҫ—ж„ҸеҲҶйҮҺгҒ§гҒҷгҖӮж—ҘеёёжҢҒгҒЎеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҒ„гӮӢжғ…е ұгӮ„гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’з”ҹгҒӢгҒ—гҖҒдјҒз”»гғ»еҸ–жқҗгғ»еҹ·зӯҶгғ»з·ЁйӣҶжүҝгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ ж¬ЎгҒё вү«
ж¬ЎгҒё вү«