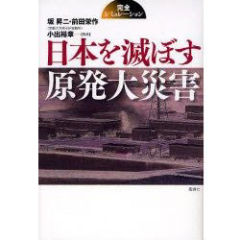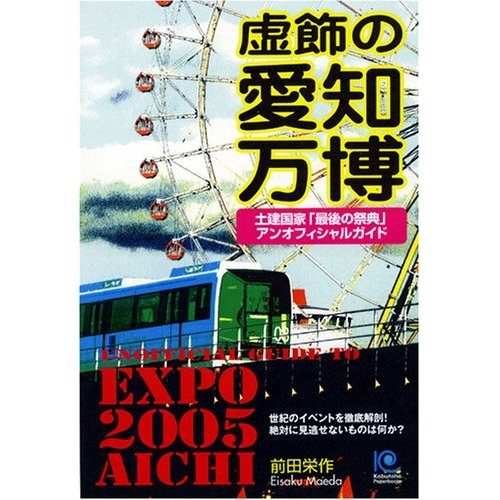「昭和十七年生まれがいなくなったなら……」<たった一度の祖父母の喧嘩・暴れる天竜川>福井 章著
 たった一度の祖父母の喧嘩
たった一度の祖父母の喧嘩
大晦日と正月を家族全員で楽しく過ごすと、両親と兄弟は帰京した。大人になってその時のことを思い出してみると、自分の人生の中で一番平穏で幸せな時期であったように思えてくる。
再び祖父母と三人の生活となった。久しぶりに会った両親や兄弟が東京へ戻っても、寂しいとは感じなかった。単に土いじりをしていただけかもしれない畑仕事の手伝い、虫を追いかけまわしたり、蛇の卵を見つけると川の中へ放り投げたり割ったりするなど、たわいのないことが実に楽しかった。
祖母が作ってくれた簡単なフンドシの上に、夏は金太郎さんの腹巻をして天竜川で水遊び、それ以外の時期は絣の着物、足には祖父が毎日のように編んだワラジを履いていた。
祖母と焚き木にする流木を拾いによく出かけた天竜川の河原の少し上流に国鉄(現JR)東海道線の鉄橋が架かっている。その上を煙を吐きながら列車が通る時、必ず汽笛が鳴った。祖母の手を握り、黙って鉄橋の上を通過していく列車を見送るのが好きであった。
戦争が始まる前までの祖父母は、何不自由のない暮らしであったという。ところが戦争が始まってから納屋を改造した家に住み、粗末な食べ物しか口にできない生活を続けていた。それでも口げんかもせず、毎日が楽しそうであった。そんな二人がけんかしているところを一度だけ見たことがある、原因は私であった。
今でこそおかずやおいしいスイーツとして食べられているサツマイモであるが、当時は貴重な主食でもあった。植えたサツマイモはすべてその年に収穫して食べるのではなく、いくつかは翌年育てるための種イモとなる。その種イモが育ち、直径四センチ、長さ十三センチくらいになった時、祖母が採ってきて、ふかして私に食べさせてくれた。「アッ君、おいしいよ、ほら食べな」といっているところへ祖父が帰ってきた。
「もっと大きく育ってから、お腹いっぱい食べさせればいいだろう」と祖父が怒鳴った。祖母は「全部採ってきたわけじゃないし、早く食べさせてやっただけじゃないか」と言い返した。お互い、しばらく言い争っていた。祖父母の激しい言い争いを初めてみた私は怖くなって泣き出した。私の泣き声に二人は口をつぐみ、それでけんかは終わった。
ところでサツマイモの中でも干しイモにしたものが一番好きであった。普段口にするものの中では最も甘かった。作り方はふかして柔らかくなったイモの上から糸を巻きつけてグイと引っ張り薄くカットする。それを竹で編んだ笊にいれ、風通しの良い軒下で数日間吊るす。黄金色になった頃が一番おいしかった。
毎日の食べ物にも事欠く東京とは違い、掛塚はお腹がいっぱいになるだけ食べることができた。自然を相手に楽しい毎日を過ごしていた。だが、そんな充実した日々が間もなく終わろうとしていた。
昭和二十三年、東京裁判でA級戦犯に対する死刑判決が出たり、お隣の国では李承晩大統領が済州島で島民を大量殺戮するなどの事件もあったが、世の中は少しずつ落ち着きを取り戻しつつあった。
この年の正月も餅を搗き、雑煮をいただき、楽しく過ごした。御屠蘇気分も冷めやらぬ頃、「アッ君も来年からは小学生だね、まだ少し早いけど、東京の生活に慣れておかないといけないから、もう少し温かくなったらお母さんが迎えに来るから、東京のお家へ帰ろうね」と祖母から言われた。
私が生まれたころ、兄はすでに小学生であった。しかし十歳も年が離れており、私は物心がついたころから掛塚で暮らしていた。兄が小学校へ通っている姿は記憶になかった。小学校という言葉を聞いたのはこの時が初めてであった。当然、小学校とはどういうもので、そこで何をするのかも知らなかった。そのため、祖母のいうことを理解することもなく「うん、わかった」と元気よく答えた。
このころになると、祖母は平仮名や、漢字で自分の名前の書き方、一から百までの数字の数え方などを一生懸命に教えてくれた。ただ、私は掛塚での生活がこのままずっと続くものだと考えていた。
日差しが随分と温かくなり、近所の家の庭の桜が満開になった。そんなある日、母が一年前に生まれたばかりの妹を背負い、弟の手を引いて掛塚へやって来た。東京もだいぶ落ち着き、食料事情もかなり良くなった。主人(私の父)も大和証券へ就職し、生活も安定してきた。小学校へ入学するまでまだ一年あるが、それまでに東京での暮らしに慣れさせておきたい。明日にでも連れて帰りたいので、祖父母から言い聞かせてやってもらえないかと言った。
小学校の話は新年早々祖母から聞かされてはいたが、明日にでも母親と一緒に東京へ帰ろうという言葉に反応し、三歳、四歳のころに経験したひもじい生活が瞬時によみがえった。思わず「いやだっ」と大声を上げると、祖母の背中にしがみつき、「帰らない、東京には帰らない。僕はおばあちゃん、おじいちゃんと、ずっとここにいる」と泣きながら叫んだ。
母が「ねえ、こっちへ来てお母さんのいうことを聞いて」と手を差し伸べるのだが、その手を振り払うようにして逃れ、祖父にしがみついた。こうした場面が何回か繰り返され、母も今日は説得できないと諦めた。入学まではまだ一年あるから、少しずつ言い聞かせ、連れ戻すのは半年後にしようということになり、母と弟妹は帰って行った。こうしてしばらくはこれまでのように自然と戯れながらの楽しい生活を続けられることになった。
暴れる天竜川
いつもは穏やかな表情を見せている天竜川だが、時には自然の恐ろしさ見せつけてくることがある。駄々をこね、東京へ戻ることを拒否し、祖父母との三人でのんびりとした毎日が続いていた七月のことであった。あまりにも強烈であったため、その日の出来事は私の脳裏にしっかりと焼き付けられている。
その日もいつものように朝食を済ませると、祖父はリヤカーを引いて畑仕事へ出かけて行った。祖父を見送った後、祖母は洗濯物をして、二人で昼食をとった。昼過ぎ、背中に鍬や鎌を入れた籠を担いだ祖母と私は天竜川の中州にあるもう一つの畑へ出かけた。
天竜川はいつもと変わらず静かに流れていた。中州へ行くためには水の中を渡る必要があった。もっとも、子どものくるぶし程度の深さしかない。畑へ着くと、いつものように河原のアマジを掘ってその根をかじり、川に向かって石投げをして遊んでいた。
祖母が収穫した野菜をかごに入れる。空は晴れていた。川に石を投げていたら、何となく水の流れが普段より早く感じられた。しばらく見つめていると、茶色の水がスーと流れてきた。
初めて見た不思議な光景に、「おばちゃん、川に赤い水が流れているよ」と大きな声を出した。祖母は川面を見るや否や、慌てた様子で収穫した野菜も鍬や鎌などの農機具も放ったらかしにしたまま、素早く私の手を引いて堤防に向かって走り出した。その時、くるぶしまでしかないはずの水は脛のあたりまで増していた。中州の畑から堤防までは二〇メートルほどしかない。だが、茶色く濁った水は流れが早くなり、水かさもどんどん増えていた。水の中で思うように足が前へ進まない。
「ばあちゃんの背中に乗れ。早く」これまで一度も聞いたことのない激しい口調で祖母が怒鳴り、前かがみになった。声の激しさと水の色や流れの変化に、ただならぬことが起きているのだろうということは理解できた。急いで祖母の背中に飛び乗った私をおんぶした祖母は走り出した。歯を食いしばり、必死の思いで堤防の下までついた時、水かさは祖母の膝近くにまで達していた。
本来であれば河原となっているはずのところが川底となっていた。堤防の下の部分は水をかぶり濡れている。しかも体重の増えた子どもをおぶっている。普段は難なく上ることができる堤防のはずだが、足が滑り、上るのに苦労していた。
「ホレッ。草をしっかり掴んで登れ」といって、私を背中から放り投げるように降ろすと、祖母も草をつかんで必死に這い上がった。
その場から逃げるように、何もしゃべらず必死に家まで帰った。家についた祖母はやっと安堵の表情を見せ「危ないところだったね」といった。
その日、掛塚の辺りは晴れていたが上流で降った大雨によって、天竜川が一挙に増水したのだ。水かさは堤防と同じ高さまで増え、いつ決壊するかもしれない状態となった。その日の夜から明け方まで、村の男衆が警戒に当たり「堤防が切れるぞ!」と怒鳴りながら走り回っていた。私たちもいつでも避難できる準備をして寝ずにいたが、堤防は切れることなく無事に済んだ。
・・・・・<別れの日・終わらない戦争の傷跡・あとがき>最終回へつづく

 福祉系情報誌の編集は得意分野です。日常持ち合わせている情報やネットワークを生かし、企画・取材・執筆・編集承っております。
福祉系情報誌の編集は得意分野です。日常持ち合わせている情報やネットワークを生かし、企画・取材・執筆・編集承っております。